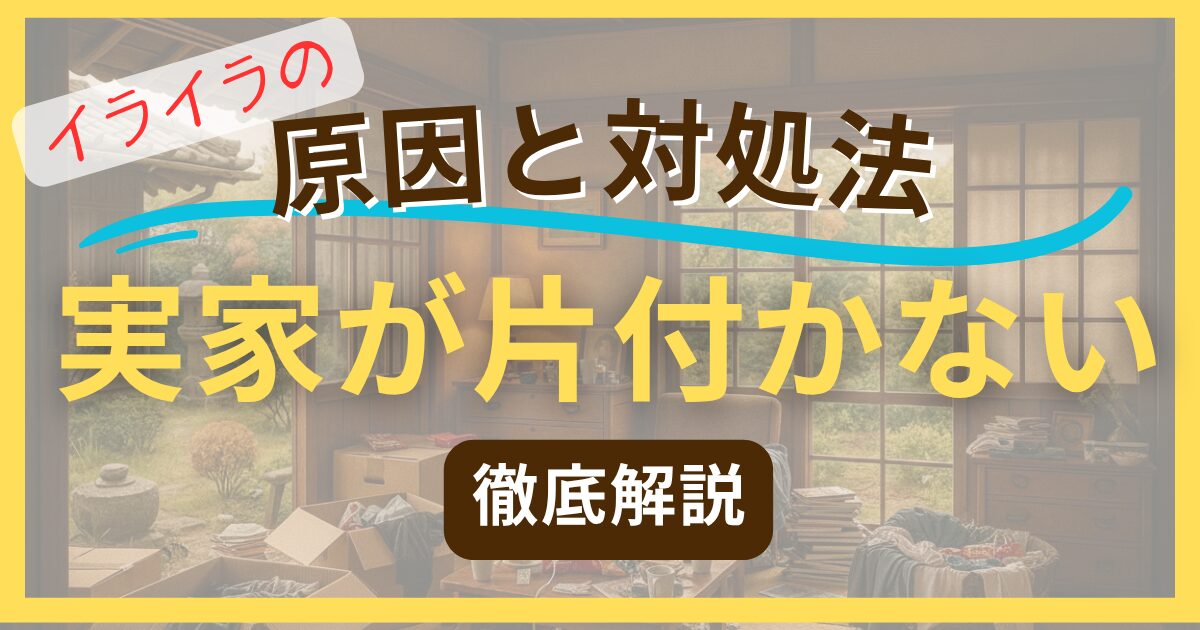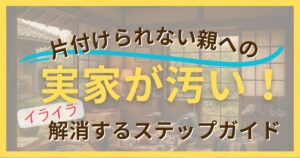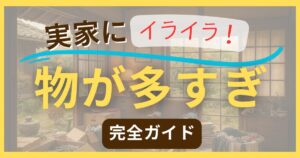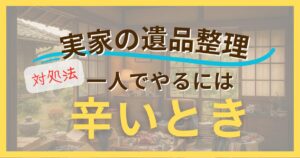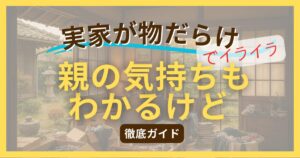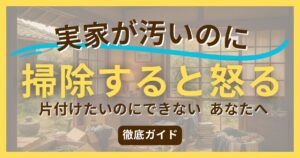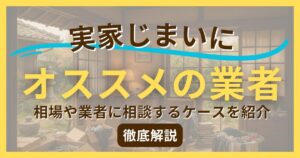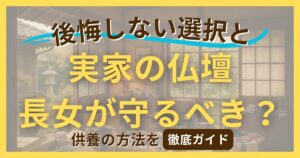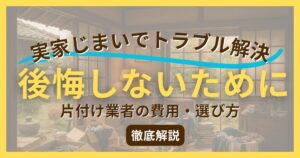ラザ
ラザ「実家に帰るたびにモノの山に圧倒される…」



「片づけたいのに、親が怒るから手を出せない…💦」



「自分の家はスッキリしてるのに、実家だけ異世界みたい😣」
こんなモヤモヤ、感じたことはありませんか?
実家が物であふれていると、帰省するたびにイライラしてしまう人は少なくありません。
親との価値観のズレや、片づけに対する意識の違いが積み重なり、感情が爆発してしまうケースも…。
この記事では、「実家 物が多い イライラ」と感じる原因を整理し、実践的な対処法を紹介します。
私自身の体験談も交えながら、親との関係を壊さずにスッキリ片づけを進めるコツをお伝えします。
結論:実家が物であふれてイライラするのは“自然な感情”!冷静な対応と計画的な片づけがカギ
親の世代と自分の世代では、物に対する価値観が大きく違います。
イライラを抑え込むのではなく、その感情を整理しながら、感情的にならずに一歩ずつ片づけを進めることが重要です。
話し合いと行動を組み合わせることで、親との関係も良好に保ちつつ、快適な空間を作っていけます。
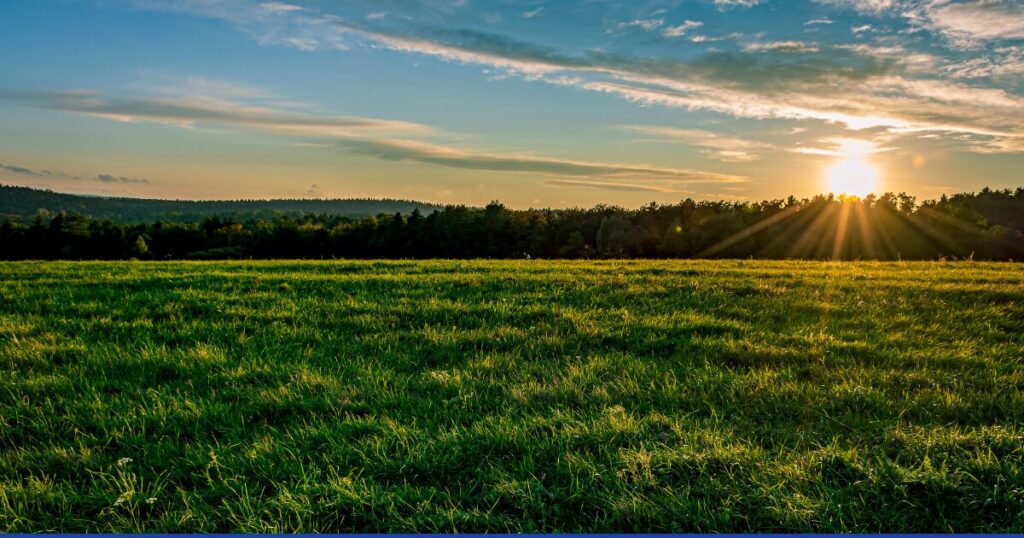
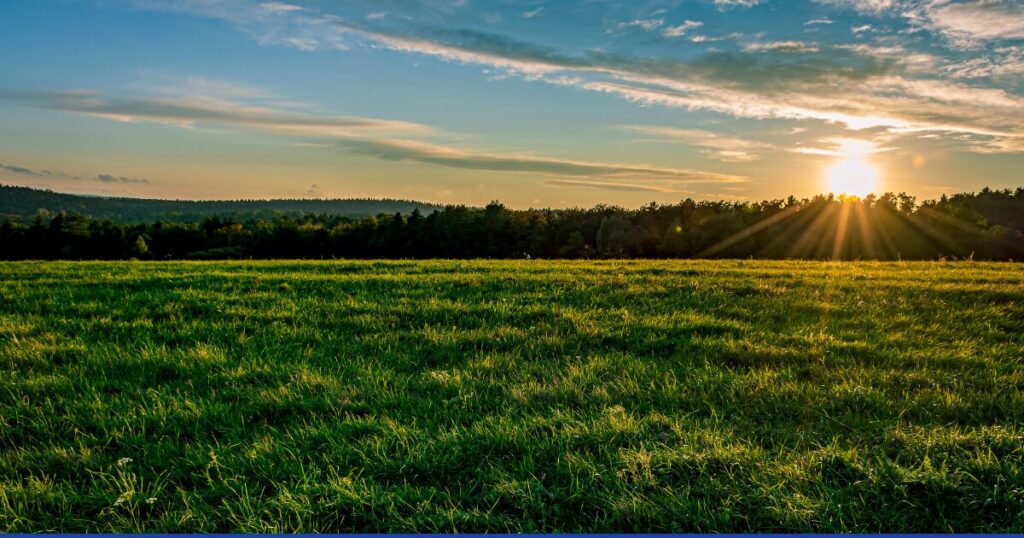
実家 物が多い イライラの根本原因を理解する
「なんでこんなに物を捨てられないの!?」と思った経験、ありませんか?
実家に物が多い背景には、世代間の価値観の違いや、親の生活習慣・心理的な背景が深く関わっています。
単に「片づければいい」という話ではなく、心の部分を理解することが、イライラを減らす第一歩ですここでは、実家の物の多さにイライラする原因を、3つの観点から整理します。
原因を知ると、感情の整理がしやすくなり、無駄なケンカも減らせますよ。
親世代は「モノを大切にする時代」を生きてきた
戦後から高度経済成長期を過ごした親世代は、物を簡単に手に入れられなかった時代を生きています。
そのため、「もったいない」という意識が非常に強く、壊れた家電や使わない服でも「いつか使える」と思って保管し続ける傾向があります。
例えば、私の母も「壊れたミシン」を20年以上押し入れにしまいっぱなしでした。
「修理したら使える」と言いながら結局使わず…。
こうした価値観の違いを知らずに「なんで捨てないの!?」とぶつかると、お互いにイライラが募ってしまいます。


「思い出の品」が捨てられずに山積みになる
親にとって、実家の押し入れやタンスに詰まった品々は、ただのモノではなく“人生の記録”でもあります。
古い写真、子どもの作品、旅先のお土産など、一つひとつに物語があり、捨てる=思い出を手放す感覚になるのです。
私の実家でも、私の小学校の作品や賞状が段ボール3箱分ありました。
「懐かしいから取っておきたい」という気持ちは理解できますが、家全体が圧迫される原因にもなっています。
加齢による片づけの体力・判断力の低下
年齢を重ねると、片づけ作業そのものが負担になります。
また、「どこから手をつけていいかわからない」という判断力の低下も影響します。
その結果、物が少しずつ積み重なり、気づいたときには家全体が“倉庫状態”になってしまうのです。
母が70代になった頃、重い家具や段ボールを動かすのが辛くなり、押し入れの奥のものは10年以上触っていませんでした。
こうした状況を理解せずに「早く片づけて!」と迫ると、イライラがぶつかり合うだけになってしまいます。
実家 物が多い イライラの原因は「親との価値観のズレ」から生まれる
実家が物であふれていると、つい「なんで片づけないの!?」と感情的になってしまいがち。
でも、イライラの根っこには“親と子の価値観のズレ”があります。
親にとっては大切なモノでも、子にとってはただの不要品というケースは珍しくありません。
このギャップが埋まらないまま強引に片づけを進めようとすると、親は防衛的になり、子はますますイライラ…と悪循環に。
ここでは、価値観のズレが起きやすい3つのパターンを紹介します。
原因を知ることで、無駄な衝突を減らし、片づけをスムーズに進められるきっかけになりますよ。


親は「モノ=安心」、子は「モノ=負担」と感じやすい
親世代にとって、たくさんの物がある家は「豊かさ」や「安心」の象徴です。
一方で、子世代にとっては「掃除が大変」「管理が面倒」という“負担”として映ることが多いです。
私の友人は、帰省するたびに母親の「いつか使う用」の紙袋が廊下を占領していて、「通るたびにストレス!」と嘆いていました。
親は安心感、子は圧迫感——この認識の違いが、イライラを引き起こします。
「捨てる=否定された」と感じる親の心理
親にとって思い出の品や長年使ってきた家具は、自分の人生そのもの。
子が「これいらないでしょ?」と軽く言ったつもりでも、親は「自分を否定された」と感じて傷つくことがあります。
私も母の洋服を整理しようとした時、「まだ着られる!勝手に捨てないで!」と泣かれた経験があります。
物ではなく“気持ち”に寄り添う姿勢が、スムーズな片づけには欠かせません。
「今の暮らし」と「昔の暮らし」のズレ
昔は“人を家に招く文化”が強く、客用の食器や布団、冠婚葬祭用品などをしっかり揃えるのが当たり前でした。
でも現代はライフスタイルが変わり、そうした物が使われる機会は激減しています。
親は「昔は必要だった」から残しているのに、子は「今は使わない」から捨てたい。
このズレを理解せずに話し合うと、「何もわかってない!」と親が怒ってしまう原因になります。
実家 物が多い イライラを抑えるには“心構え”が大切
実家の物の多さを目の前にすると、ついイライラが募ってしまいますよね。
でも、感情のままに行動すると親との関係が悪化したり、片づけが逆に進まなくなってしまうこともあります。
まず大切なのは、自分の心を整えること。心構えを変えるだけで、イライラをコントロールしながら冷静に片づけに向き合えるようになります。
ここでは、実家の片づけでイライラしないための3つの心構えを紹介します。
少し意識を変えるだけで、親との関係もグッと柔らかくなりますよ。


「すぐには変わらない」と心得る
親世代の価値観や習慣は、長い年月をかけて築かれたもの。数日や一言で変わるものではありません。
私も最初は「一気に片づけたい!」と意気込んで実家に帰省しましたが、母の反応は大ブレーキ。
最終的に半年以上かけて少しずつ進める形に落ち着きました。
焦る気持ちを抑え、「今日は一箇所だけ」と小さなゴールを設定するだけでも、イライラが軽減されます。
「親の“気持ち”に寄り添う」姿勢を持つ
片づけを進めるときは、「モノを減らす」よりも「親の気持ちを尊重する」ことを優先すると、対立が減ります。
例えば、「この服はもう着ないでしょ?」と攻めるのではなく、「これはどんな時に着てたの?」と話を聞くと、親も心を開きやすくなります。
思い出話を通して自然に「これは手放してもいいかな」という気持ちになることも多いです。
「イライラしたら一旦離れる」を徹底する
片づけの途中でイライラがピークに達したら、その場で無理に話し合いを続けるのは逆効果です。
深呼吸して別の部屋に移動したり、お茶を飲んでクールダウンするだけで、感情の衝突を防げます。
私は母と押し入れを整理している最中に、意見がぶつかって泣きそうになったとき、一旦ベランダに出て風に当たりました。
その後、落ち着いて再開したら話もスムーズに進んでビックリ!感情をリセットする習慣、大事です。
実家 物が多い イライラを減らすには「事前の準備と話し合い」が超重要
実家の片づけは、勢いだけで突っ込むと高確率で親子ゲンカになります。
「片づけたい!」という気持ちが強くても、親との話し合いや準備を怠ると、親は防衛的になり、こちらはイライラが募ってしまう…まさに負のループ。
逆に、しっかり準備しておけば、親の気持ちを尊重しながら少しずつ片づけを進められます。
ここでは、片づけをスムーズに始めるための具体的な準備と話し合いのコツを3ステップで紹介します。
「片づける目的」を親と共有する
最初に「なんで片づけたいのか」を親と共有することが大切です。
例えば、「地震のときに危ないから」「将来的に介護が必要になった時、移動しやすいように」など、感情ではなく“安全性や将来の安心”を理由に伝えると、親も耳を傾けやすくなります。
私の場合も「お母さんが転んだら危ないから」と安全面を伝えたら、最初は拒否していた母が少しずつ納得してくれました。
「片づける範囲とスケジュール」を明確にする
「全部まとめて片づけよう!」は絶対NG。
一度に広範囲を片づけようとすると親も混乱するし、自分も疲れて途中でイライラが爆発します。
「まずは押し入れの上段だけ」「次は玄関周りだけ」など、範囲とスケジュールを具体的に決めることで、無理なく進められます。
1回の作業時間は2〜3時間以内が目安です。
「第三者」を交えて話すと冷静になれる
親子だけで話し合うと、どうしても感情的になりやすいもの。
親が信頼している親戚やケアマネ、地域包括の職員など第三者を交えると、冷静に話が進むことが多いです。
私の家では、母が昔から信頼している伯母に同席してもらったところ、母の態度がガラリと柔らかくなりました。
親にとって身内以外の“中立的な立場”の人の意見は、意外と素直に聞いてくれるものです。
実家 物が多い イライラを防ぐ片づけの“実践テクニック”3ステップ
「準備と話し合いはしたけど、いざ始めると全然進まない…。」
そんな声、本当によく聞きます。
実家の片づけは思った以上に時間がかかるし、感情も絡むから一筋縄ではいきません。
でも、ちょっとしたコツを押さえるだけで、イライラを減らしながらスッキリ片づけを進められる。
ここでは、実家の片づけを実践する際に役立つ3つのテクニックを紹介します。
親の気持ちに寄り添いながらも、着実にモノを減らしていける方法です。
「思い出ゾーン」と「実用品ゾーン」を分ける
片づけを始めると、どうしても“思い出の品”が出てきて手が止まりがち。
そんなときは、「思い出ゾーン(あとで一緒に見返す箱)」と「実用品ゾーン(今使っているもの)」に分けるだけで、作業の手が止まりにくくなります。
私の実家では「思い出箱」を用意して、迷ったものはとりあえずそこへ入れるルールにしたら、母も安心して仕分けできるようになりました。
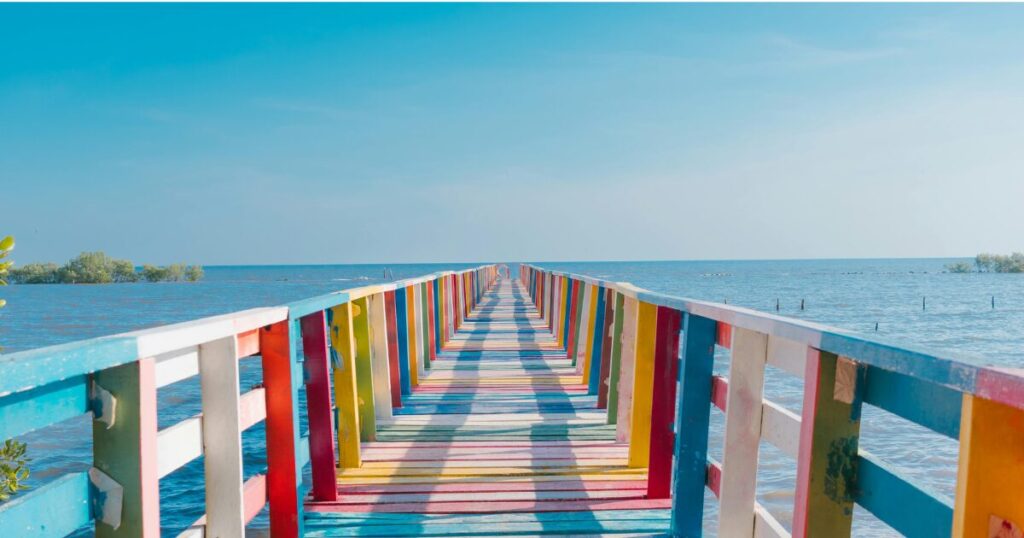
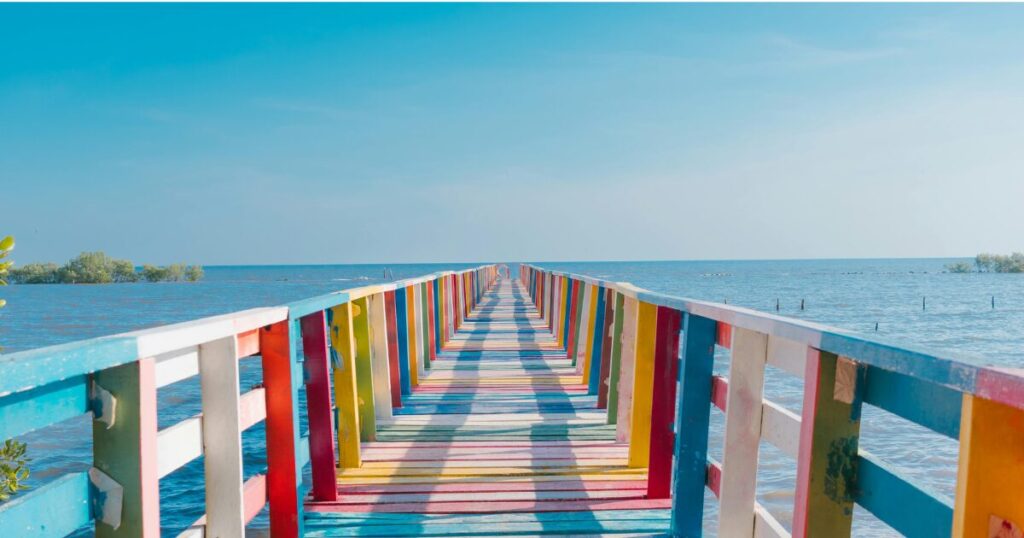
「親の“YES”を引き出す質問」を使う
「これいらないよね?」と聞くと、親は反射的に「いる!」と答えがち。
そんなときは「これ、最近使ったのいつ?」「もし捨てたら何が困る?」と具体的な質問に変えると、親も冷静に考えやすくなります。
私も母に「この鍋、最後に使ったのいつ?」と聞いたら「…15年前かも」となり、あっさり手放せたことがありました。
「一気に捨てる」より「少しずつ繰り返す」を意識する
実家の片づけを一度で完璧に終わらせようとするのは無理ゲーです。
一気にやろうとすると親も疲れるし、自分も途中でイライラしてギブアップ…。
「月に1回帰省して1エリアずつ」「週末ごとに1段だけ」など、少しずつ繰り返す方が結果的に早く進みます。私も玄関→押し入れ→リビングの順に半年かけて進めたら、母の抵抗もどんどん減っていきました。
実家 物が多い イライラを減らす“親への声かけ&伝え方”のコツ
実家の片づけを進めるとき、親とのやりとりがうまくいかずにイライラが爆発すること、ありませんか?。
実は、片づけの成功は「声かけ次第」と言っても過言ではありません。
同じ内容でも、伝え方ひとつで親の受け取り方が180度変わるんです。
ここでは、親を傷つけず、気持ちよく協力してもらうための声かけと伝え方のコツを紹介します。
ちょっとした言い回しを変えるだけで、雰囲気がガラッと変わりますよ。
「否定」ではなく「共感+提案」で話す
「これもういらないでしょ!」といきなり否定から入ると、親は構えてしまいます。
「懐かしいね〜!でも、今は使ってないし、別の場所にしまうのはどう?」のように、まずは共感を示してから提案するのが効果的です。
私も母の古い雑誌を前に「またこれ!?」とイラッとしたことがありますが、「当時流行ってたもんね!でも今は読まないよね。」
と言い方を変えたら、すんなり処分OKが出ました。


「一緒にやろう」のスタンスで寄り添う
「片づけてよ!」と丸投げするのではなく、「一緒にやろう。」の姿勢を見せるだけで、親の気持ちは全然違います。
私も最初は母に「これ整理しといて」とお願いしたら全く進まず…。
でも一緒に押し入れを開けながら「これ懐かしいね〜!」と話をしつつ進めたら、驚くほど協力的になってくれました。
“やらされている”から“自分も参加している”に意識が変わる瞬間です!
「小さな成功体験」を一緒に喜ぶ
片づけが進んだときは、思いっきり褒めて一緒に喜ぶのがポイントです。
「玄関めっちゃスッキリしたね!」「ここ片づけたら気持ちいいね〜!」と声をかけることで、親の中に「片づけ=気持ちいいこと」というポジティブな印象が残ります。
私の母も、最初は片づけに消極的だったのに、「ここ綺麗になったね!」を繰り返すうちに、次第に自分から「次ここやろっか」と言い出すようになりました。
実家 物が多い イライラ…片づけが進まないときの対処法
どれだけ準備しても、話し合っても、うまくいかないときってありますよね。
親がなかなか手放してくれなかったり、自分が忙しくて進められなかったり…。
思い通りに進まないと、イライラや無力感で投げ出したくなる瞬間もあります。
でも、ここで踏ん張りどころ!焦らず、柔軟に対処することで、少しずつでも確実に進めることができます。
ここでは、片づけが停滞したときに実践したい3つの対処法を紹介します。
「一箇所だけでも進める」を意識する
全部を一気に片づけようとすると挫折しやすいです。進まないときこそ、「一箇所だけでも片づける」を徹底すると、気持ちがグッと楽になります。
私も母の実家の片づけで、リビングが全く進まなかったとき、まずは靴箱だけを整理したら、「ここキレイになったね!」と母のやる気が少し戻ってきました。
小さな達成感が、次のステップへの原動力になります!
「親のタイミング」を尊重する
親がなかなか手放さないときは、こちらがどんなに急かしても逆効果です。
無理に進めず、「また今度この話しよっか」と一旦引くことで、親の中に「考える時間」が生まれます。
私の母も、古い着物をなかなか手放せなかったけど、半年後に「やっぱり処分しようかな」と自分から言い出しました。
“親のペース”を尊重することは、イライラを減らす秘訣のひとつです。
「プロの力を借りる」選択肢を持つ
家族だけで限界を感じたら、思い切ってプロに頼むのも大きな一歩です。
遺品整理や生前整理の専門業者は、モノの仕分け・運搬・処分まで一気に対応してくれるので、想像以上にスムーズに進みます。
私の友人は、長年放置されていた物置をプロに依頼して1日でスッキリ。「自分たちだけで抱えなくてよかった〜!」とホッとしたそうです。
実家 物が多い イライラを爆発させない!親との関係を壊さないための注意点
実家の片づけは、モノを整理するだけじゃなく「親との関係」が大きなカギになります。
せっかく片づけを始めても、途中でケンカになって関係がギクシャクしてしまったら本末転倒。
片づけを“親と協力して進めるプロジェクト”として捉えることが大切です。
ここでは、イライラを爆発させず、良好な関係を保ちながら進めるための3つの注意点を紹介します。
ちょっと意識を変えるだけで、空気がグッと柔らかくなりますよ。
「片づけ=親の否定」にならないよう注意する
親が物を手放さない背景には、長い人生や思い出があります。それを「なんで捨てないの!?」と否定すると、親は傷ついてしまいます。
「お母さんの大切なものだからこそ、一緒に見直したい。」という伝え方に変えるだけで、受け取り方が全く違ってきます。
私も母の思い出の品に「これもういらないでしょ」と言ってしまい、泣かせた経験が…。
そこから反省して、共感をベースに話すように変えました
「怒りの感情」をその場でぶつけない
片づけの最中は、思わぬひと言でイライラが爆発することもありますよね。
でも、感情をそのままぶつけると、親子関係にヒビが入る原因に…。
私の場合も、母の「これ全部取っとく!」にブチッときそうになった時、一旦その場を離れて深呼吸☁️ 10分後には冷静に戻って、話し合いを再開できました。
怒りを一度リセットする習慣、大事です!
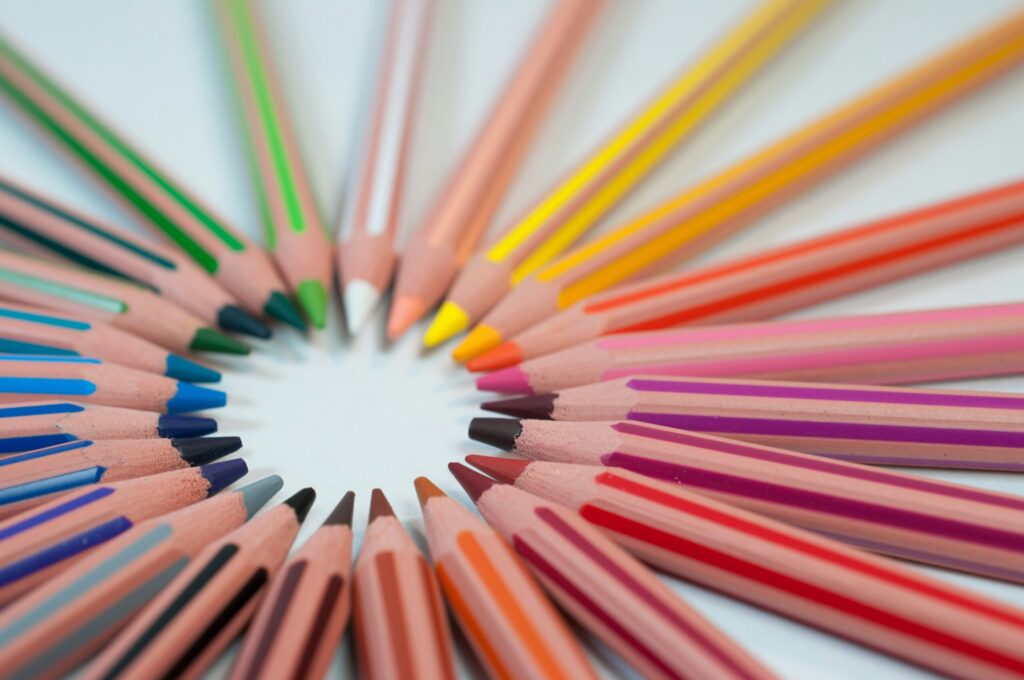
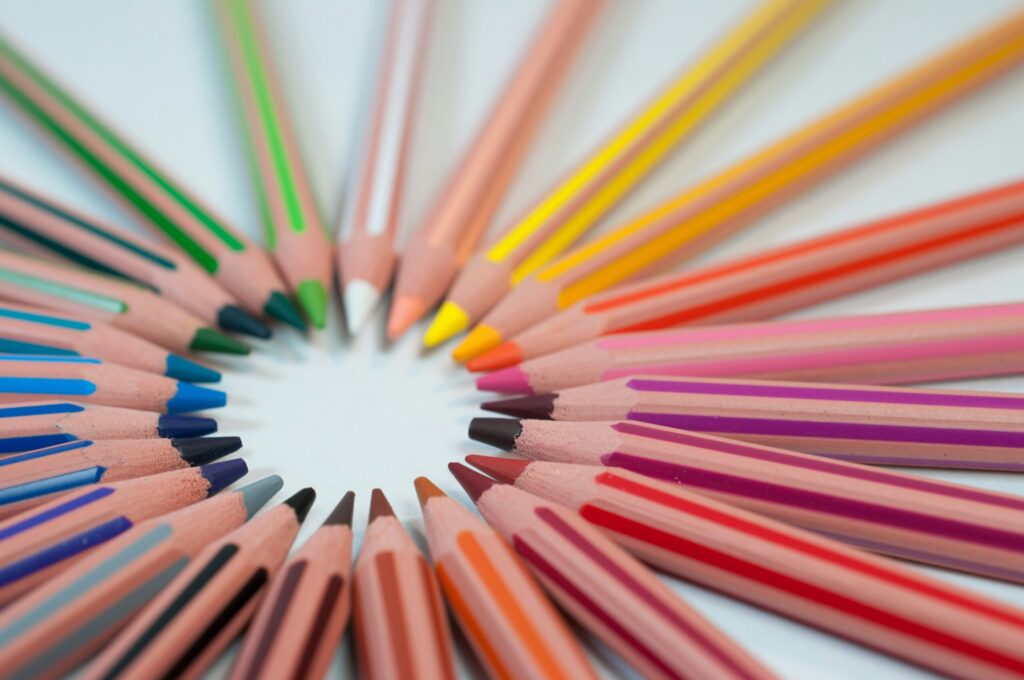
「片づけ=親孝行」の意識を持つ
片づけは「モノを減らす作業」ではなく、実は親の今後の生活を守る“親孝行”でもあります。
「転倒の危険を減らす」「介護が必要になったときの準備」など、未来の安心につながる行動なんです。
私は母に「今一緒に片づけるのは、お母さんがこれからも元気で快適に過ごせるようにするためだよ。」と伝えたら、母も納得して協力的になりました。
実家 物が多い イライラを減らす“タイミング&季節”の工夫
実家の片づけって、実は「いつやるか」で成果が全然変わってきます。
親の気分・気候・行事などのタイミングをうまく使えば、自然と親も協力的になり、イライラも最小限で済むんです。
逆に、忙しい時期や真夏・真冬などに強行すると、親も自分も疲れてギスギスしてしまうことも…。
ここでは、実家の片づけをスムーズに進めるための“ベストなタイミング&季節のコツ”を紹介します。
「親が気持ちに余裕のある時期」を選ぶ
親の気分や体調がいい時期に合わせるのはめちゃくちゃ大事です
例えば、介護や病気の不安が少ない時期、季節の変わり目などは気持ちに余裕があることが多く、話し合いや作業がスムーズに進みやすいです。
私も母の病院通いが落ち着いた春先に話を切り出したら、想像以上に前向きに聞いてくれました。


「季節のイベント」をきっかけにする
お盆・年末・新年度などのイベントは、片づけの絶好のチャンスです。
「帰省したついでに玄関だけ片づけようか。」など、行事を自然なきっかけにすると、親も抵抗感が少なく始めやすくなります。
私の実家でも、年末の大掃除をきっかけに少しずつ押し入れの整理を進めたら、母も「せっかくだから」と前向きになってくれました。


「暑すぎ・寒すぎ」は避けるのが鉄則
真夏や真冬に片づけを強行すると、親も自分も疲れ切って途中でギブアップ…なんてことになりがち。
特に高齢の親は体力面への影響も大きいので、春や秋などの過ごしやすい季節がベストです。
私も真夏に物置の片づけを強行して、母と2人で汗だく&イライラMAXになった苦い経験があります。
実家 物が多い イライラを繰り返さないための“維持と仕上げ”のコツ
片づけが終わって「やっとスッキリ〜!」と安心しても、油断するとあっという間に元通りになってしまうのが実家あるある…。
実は、片づけの本番は「終わったあと」なんです。
少しの工夫でキレイな状態をキープできれば、イライラの再発も防げて、親も自分も快適な空間を長く楽しめます。
ここでは、片づけた実家をリバウンドさせないための3つのコツを紹介します。
「置き場所ルール」を親と一緒に決める
モノがまた増える最大の原因は、“戻す場所が決まっていない”こと。
片づけたあとに「ここに戻す」「この箱に入れる」といったシンプルなルールを親と共有すると、キレイが長続きします。
私の実家では、郵便物を入れる専用のカゴを玄関に置いたら、紙類が散らかるのが激減しました。
「定期的な見直し日」を設定する
一度片づけても、年月が経てばまたモノは溜まっていきます。
「年末の大掃除に合わせて押し入れをチェック」「春に衣替えついでに棚を見直す」など、年に1〜2回の定期チェック日を決めておくと、リバウンド防止になります。
私も母と「お盆前と年末は見直しの日」に決めたことで、以前のような“モノの山”に逆戻りすることがなくなりました。
「プロのサポート」を定期的に活用する
高齢になると、維持するのも大変になっていきます。そんな時は、定期的に専門業者にお願いするのもおすすめです。
重い家具の移動や不用品の回収など、プロに頼むことで無理なくキレイをキープできます。
私の友人は、年1回だけ業者にお願いして「自分たちは軽い掃除だけ」にしており、親の負担もぐっと減ったそうです。
まとめ:イライラをチャンスに変えて、“親と一緒に”心地よい実家をつくろう!
実家の片づけでイライラするのは、多くの人が抱える“自然な感情”です。
でも、そのイライラの背景を理解して、少しずつ話し合いと工夫を積み重ねていけば、関係をこじらせずにスッキリと片づけを進められます。
焦らず、感情的にならず、親と歩調を合わせて進めることが最大のポイントです。


📝 よくある質問(FAQ)
- 親が全然片づけに乗り気じゃない時はどうしたらいい?
-
無理に進めず、親のペースを尊重しましょう。「安全面」など具体的な理由を伝えると心が動きやすいです。
- どこから片づければいいのか分かりません…
-
押し入れや玄関など、使用頻度が高く成果が見えやすい場所からスタートするのがおすすめです。
- 遠方に住んでいて頻繁に帰れない場合は?
-
帰省時に「1エリアだけ」を目標にコツコツ進めましょう。プロの力を定期的に借りるのも◎です。
- 親が感情的になって話が進まなくなったら?
-
一旦その場を離れてクールダウン☕。落ち着いてから再度話し合う方が建設的です。
- 費用を抑えて片づけたい場合は?
-
自分たちで仕分け&処分できる部分は自力で行い、大型家具など必要な部分だけ業者を活用するのがコツです
片づけを本格的に進めたい方へ
本格的な片づけをスムーズに進めたい方には、優良遺品整理業者紹介サービス【遺品整理110番】がおすすめです。
全国対応・相談無料で、信頼できる業者を紹介してもらえるので、安心して依頼できます。親の気持ちに寄り添いながら、プロの力で一気にスッキリさせましょう