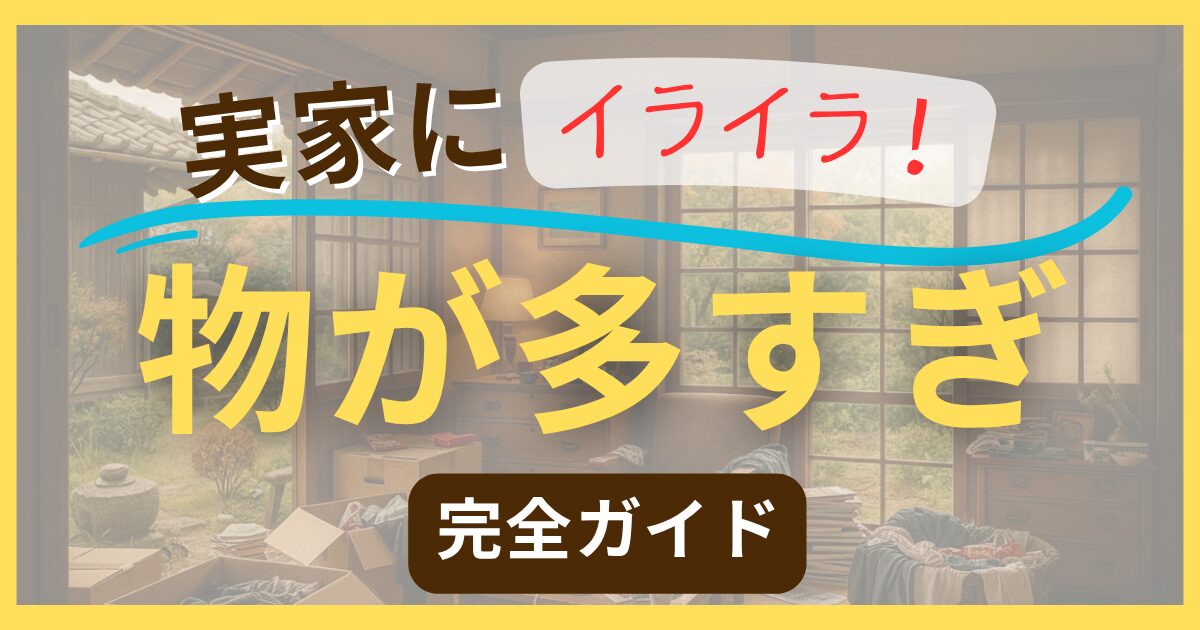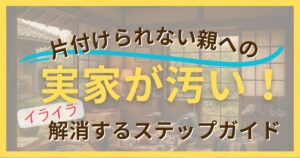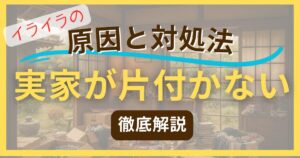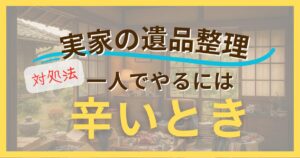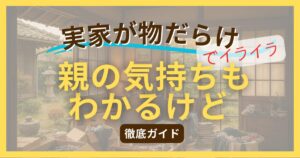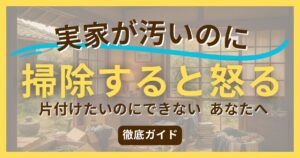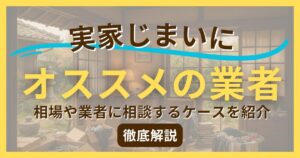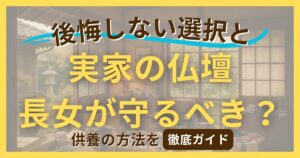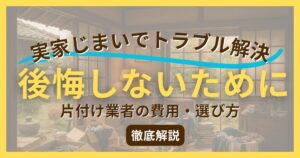ラザ
ラザ「実家に帰るたびに、物があふれていて落ち着かない…」



「片づけようとしても、親が全然動いてくれない」



「イライラして言い合いになってしまう…」
実家の物が多すぎて、気持ちが疲れてしまう経験はありませんか?
親世代と子世代では物への価値観が大きく異なり、話し合いが進まないまま時間だけが経ってしまうケースも多いです。
しかし、そのまま放置すると、転倒事故・災害時の危険・相続時の大きな負担など、さまざまなリスクが生まれます。
この記事では、「実家 物が多い イライラ」の原因と対処法を、専門的な視点+具体的なステップで徹底的に解説します。
親との話し合いのコツや片づけの進め方、業者の活用法まで幅広く紹介するので、読めば今日から少しずつ前に進めるはずです。
イライラを手放して、実家を安心で快適な空間に整えていきましょう。
実家 物が多い イライラの原因を明確にしよう
実家に帰るたびに感じる“モヤモヤ”の正体
実家に一歩足を踏み入れた瞬間、目に飛び込んでくる大量の家具や家電、そして捨てられずに積み上げられた段ボール……。
「どうしてこんなに物が多いの?」と心の中で叫びたくなる人も少なくありません。
イライラの根本には、“片づかない環境へのストレス”や“価値観の違い”など、複数の原因が隠れています。
片づかない家は心の負担になる
視界に常にモノがあふれている環境では、無意識のうちに脳が疲弊します。片づけたいのに手を出せない、両親に言っても進まない。この「やりたいのにできない」状態が続くと、次第にストレスが積み重なり、実家に帰るたびにイライラが強くなる傾向があります。
家族間の価値観のズレも原因
親世代と子世代では、“モノへの考え方”に大きな差があります。
たとえば、親は「まだ使える」「思い出がある」と残したい一方、子どもは「使わないなら処分したい」と考えがち。
この価値観のズレが話し合いを難しくし、イライラの原因になるのです。
実家 物が多い イライラを放置すると起きるリスク
片づけられない家は転倒や事故の原因になる
物が多く通路が狭い家では、高齢の親がつまずいたり転倒したりするリスクが高まります。
特に夜間や急な移動時は危険度が増し、骨折や入院につながるケースも少なくありません。
実際に、実家の廊下に積まれた新聞紙の山に足を取られて転倒した例もあり、放置は大きな危険をはらんでいます。


災害時の避難が遅れるリスク
物が多いと、火災や地震のときにスムーズに避難できない危険があります。
家具が倒れて通路をふさいだり、物が崩れて避難経路がふさがれたりする状況は想像以上に多いです。
防災の観点から見ても、「片づけない」状態を続けるのは大きなリスクになります。
相続や遺品整理で子どもに負担が集中する
親が亡くなったあと、大量の荷物を一気に整理しなければならないのは、多くの場合子どもたちです。
実家の物が多ければ多いほど、遺品整理にかかる時間・費用・精神的負担は増大します。
「今はまだ元気だから」と先延ばしにすることで、将来的に大きな負担を背負う可能性があります。
実家 物が多い イライラを減らすための第一歩は「現状把握」
実家の“物量”を数字で把握する
片づけの最初のステップは、感情的になる前に「現状を客観的に見る」ことです。
たとえば、各部屋ごとに段ボールの数や不要家具の数をざっくり数えるだけでもOKです。
物の多さを数字で見える化すると、「これは確かに多い」と自分も親も冷静に話し合いやすくなります。
親の気持ちを聞く時間をつくる
いきなり「捨てよう!」と切り出すと、親は強い拒否感を示しがちです。
まずは「どうしてこの部屋はこの状態になったのか」「この荷物はいつからあるのか」など、親の気持ちや背景を丁寧に聞く時間を設けましょう。
気持ちを受け止めてもらえると、親側の心のハードルも下がります。
“エリアを区切って”小さく始める
一度に全部片づけようとすると、途中で挫折してしまいがちです。
おすすめは「リビングの一角」「押し入れの上段だけ」など、狭い範囲を決めて少しずつ進める方法です。
小さな達成感を積み重ねることで、親も子も「やればできる」という実感を持ちやすくなります。


実家 物が多い イライラを防ぐための話し合いのコツ
感情的にならずに冷静に伝える
「なんでこんなに物をため込むの!」と怒ってしまうと、親は防衛的になり、話し合いが進みません。
まずは冷静に、自分が実家の環境でどんな気持ちになるのかを具体的に伝えましょう。
たとえば「通るたびに段ボールにつまずきそうで心配」「災害時が怖い」といったように、相手を責めず“自分の気持ち”を主語にして話すことがポイントです。
否定せずに親の意見も尊重する
親世代には、戦後の物不足や「もったいない精神」が根付いています。
「全部捨てよう」は、思い出や人生の否定と受け取られてしまうこともあります。
親の話をしっかり聞き、「この家具には思い出があるんだね」「これは残しておこう」といったように、気持ちを尊重しながら話し合う姿勢が大切です。
具体的な期限とゴールを共有する
「いつか片づけよう」では、なかなか行動に移せません。
話し合いの中で、
「来月の連休に押し入れを一緒に整理しよう」
「年内にリビングをスッキリさせよう」
など、具体的な期限とゴールを共有しておくと、親も子も動きやすくなります。
実家 物が多い イライラを解消するための片づけステップ


ステップ①:仕分けを「要・不要・保留」でシンプルに
片づけを始めるときは、複雑な基準を設けず「要る・要らない・保留」の3分類が基本です。
「とりあえず保留」を作ることで、親も即決しやすくなり、作業がスムーズに進みます。
たとえば古い食器や使っていない調理器具は、
実際に使う頻度を確認しながら仕分けするのがポイントです。
ステップ②:一時的な仮置きスペースを作る
片づけ作業中は、途中で作業が止まっても生活に支障が出ないよう、一時的な仮置きスペースを用意しておくと安心です。
たとえば、和室の一角やベランダの軒下などを活用すると、分別後のモノを整理しながら全体の見通しを立てやすくなります。
ステップ③:捨てられない物には「写真保存」も有効
親が手放せない思い出の品は、写真を撮ってデータで残すのも効果的です。
たとえば、子どもの作品や昔の旅行グッズなどは、スマホで撮影してアルバム化すれば、物理的なスペースを減らしつつ記憶を残せます。
「捨てる」ではなく「形を変えて残す」方法は、親の抵抗感を和らげるきっかけになります。


実家 物が多い イライラを減らす「プロの手」を借りる選択肢
片づけが進まないときは専門業者に依頼するのも有効
「やろう」と思っていても、実家の荷物は想像以上の量で、途中で挫折してしまうケースが多いです。
そんなときは、不用品回収や片づけの専門業者に依頼する方法もあります。
プロに任せることで、自分たちだけでは進まなかった部分が一気に片づき、精神的な負担も軽減できます。
高齢の親も安心して任せられるサポートがある
最近では、高齢者の家を対象にした「生前整理サポート」や「遺品整理士」の資格を持つスタッフが在籍する業者も増えています。
親が安心して作業を任せられる体制が整っているため、「他人に入ってもらうのは不安」という気持ちを和らげることができます。
費用相場と見積もりの重要性
業者に依頼するときは、必ず複数社に見積もりを依頼し、サービス内容と料金を比較することが大切です。
作業内容やトラックの台数、回収品目によって料金は大きく変わります。
悪質な業者を避けるためにも、口コミや実績をチェックし、信頼できる業者を選ぶのがポイントです。
実家 物が多い イライラを減らすために親世代へ伝えたいポイント
「もったいない」気持ちを否定しない
親世代にとって、
「いつか使うかもしれない」
「まだ使える」
は当たり前の感覚です。
いきなりそれを否定すると、強い抵抗を受けることになります。大切なのは、「使えるものを無理に捨てよう」とするのではなく、「今の暮らしに本当に必要か」という視点を一緒に持つことです。
気持ちを尊重しながら対話することで、協力的な雰囲気が生まれます。


「片づけ=親の人生の整理」であると理解する
実家の物には、親の歩んできた人生や思い出が詰まっています。
単なる“不要品の処分”ではなく、“人生を振り返る大切な時間”と捉えることが重要です。
たとえば、アルバムや手紙を見ながら親と昔話をすることで、自然と不要な物の仕分けにもつながることがあります。
少しずつ習慣化していく声かけをする
片づけを一度きりのイベントにするのではなく、「週末の30分だけ一緒に整理しよう」など、習慣化する声かけをすると効果的です。
親世代は急な変化を苦手とする人が多いため、少しずつペースを合わせながら進めることで、イライラも減り、前向きな協力が得られます。
実家 物が多い イライラを和らげる「心の整理」のコツ
片づけを「親孝行の一環」と考える
実家の片づけは、単に環境を整える作業ではなく、親が安心して暮らせるようサポートする“親孝行”でもあります。
「イライラする」気持ちは正直な感情ですが、「親のために安全で快適な空間をつくる」という目的を意識すると、気持ちの持ち方が少しずつ変わっていきます。


完璧を求めすぎず“7割”を目指す
実家の片づけは長期戦になりがちです。
最初から完璧を求めると、思うように進まない現実にイライラが募ってしまいます。
「今日はここだけ片づけばOK」「全体の7割で十分」と、ハードルを下げることで心の余裕が生まれ、継続しやすくなります。
自分自身の気持ちも整理する
親との価値観の違いにぶつかると、イライラや罪悪感、無力感が入り混じることがあります。
そうした感情を無理に押し殺さず、誰かに話したりノートに書き出したりして、客観的に見つめる時間をつくるのも有効です。
自分の心を整えることが、結果的に片づけの成功にもつながります。
実家 物が多い イライラを減らすために今からできる予防策
定期的なチェック日をつくる
一度片づけても、そのまま放っておくとまた物が増えてしまいます。
月に1回や季節の変わり目など、定期的な「チェック日」を設けて、不要品が溜まらない習慣をつくると効果的です。
小さな見直しをこまめに行うことで、大がかりな片づけをしなくてもきれいな状態をキープできます。
親と一緒に“持ち物ルール”を決める
「1年以上使っていなければ処分」「同じ用途の物は2つまで」など、シンプルなルールを親と一緒に決めておくと、今後の物の増加を防げます。
ルールを共有しておくことで、親も「これはルールに合わないな」と自主的に判断できるようになります。
買い物習慣を見直す
新しい物が入ってくるスピードが速いと、いくら片づけても追いつきません。
日常の買い物で「ストックがあるか確認する」「セール品を衝動買いしない」など、ちょっとした意識を変えるだけで、実家の物の増加を防ぐことができます。


実家 物が多い イライラを手放して前向きな時間をつくろう
片づけは「親子の関係を深めるチャンス」
片づけはただの作業ではなく、親との時間を共有し、思い出を語り合える貴重な機会です。
写真や昔の品を見ながら話をすると、自然と会話が増え、今まで知らなかったエピソードが聞けることもあります。
イライラばかりに目を向けず、ポジティブな側面を意識することで、親子の絆も深まります。
無理をせず、自分のペースで進める
一気に片づけようとすると、親も自分も疲れ切ってしまいます。
焦らず、自分の生活ペースと両親の体力に合わせて進めることが大切です。
完璧を目指すのではなく、「少しずつ着実に進める」ことを意識すれば、イライラを減らしながら無理なく整理ができます。
業者の力を借りて一気にスッキリする選択も
どうしても手が回らない場合は、プロの片づけ・不用品回収業者に依頼するのも一つの手です。
複数の業者に見積もりをとって比較すれば、費用を抑えつつ安心して依頼できます。
→
よくある質問(FAQ)
- 親が全然片づけに協力してくれません。どうしたらいいですか?
-
いきなり「捨てよう」と迫ると反発されやすいです。
まずは親の気持ちや物への思いを丁寧に聞き、価値観を尊重する姿勢を示しましょう。
そのうえで、小さな範囲から一緒に片づけると、協力を得やすくなります。
- 業者を使うと高額になりそうで不安です。
-
料金は業者によって差が大きいため、複数社に見積もりを取ることが重要です。一括見積もりサービスを使えば、費用やサービス内容を比較しながら安心して選べます。
- 片づけをしても、すぐにまた物が増えてしまいます。
-
定期的な見直し日を設ける・買い物ルールを決めるなど、予防策を組み込むのがポイントです。
小さな習慣を積み重ねることで、きれいな状態を維持しやすくなります。
- 実家が遠方で、なかなか片づけに通えません。
-
オンライン会議で事前に打ち合わせをしたり、地元の片づけ業者に立ち会いをお願いするなど、現地にいなくても進められる方法があります。
スケジュールを決めて段階的に進めるとスムーズです。
- 親が「全部思い出だから捨てられない」と言います。
-
写真やデータに残すなど、「捨てる」以外の方法を提案すると受け入れやすくなります。
思い出を否定せず、形を変えて残す工夫が有効です。