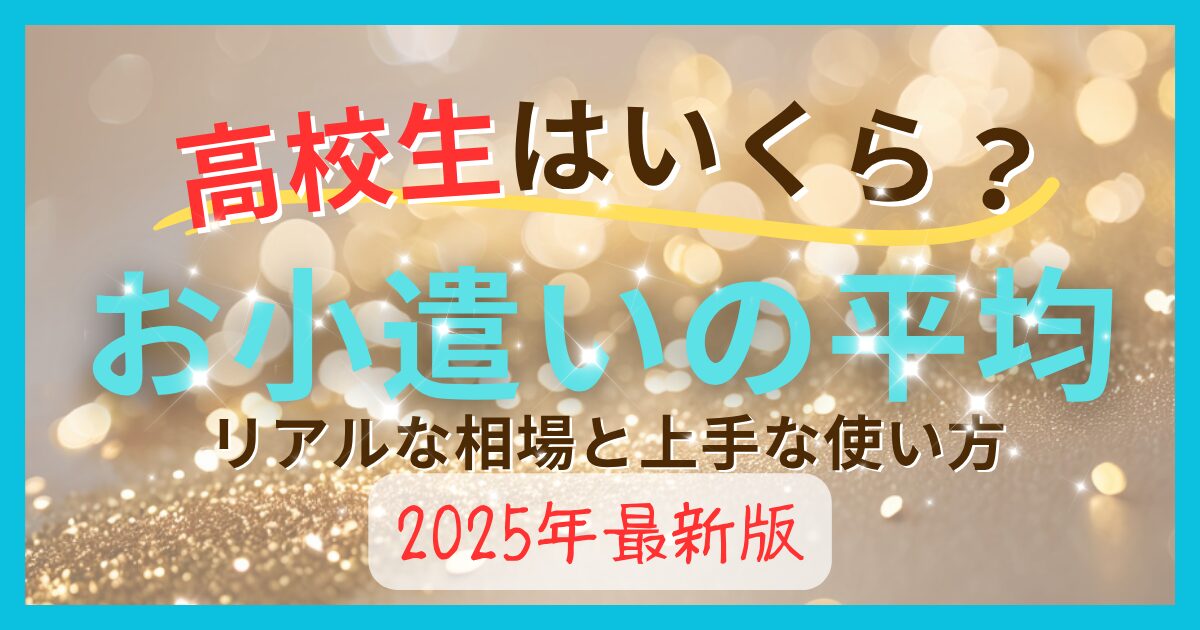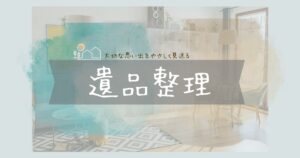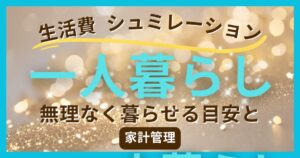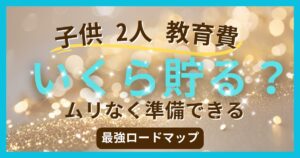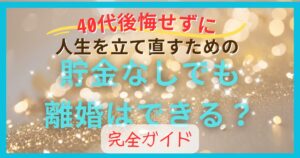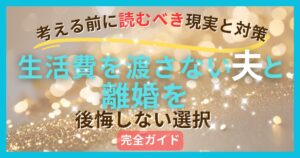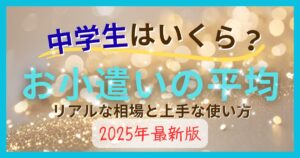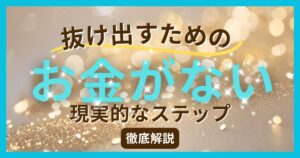ラザ
ラザ「うちの子、高校生だけど…みんな一体いくらもらってるんだろう?」



「多すぎても心配だし、少なすぎてもかわいそう…ちょうどいい金額って難しい!」
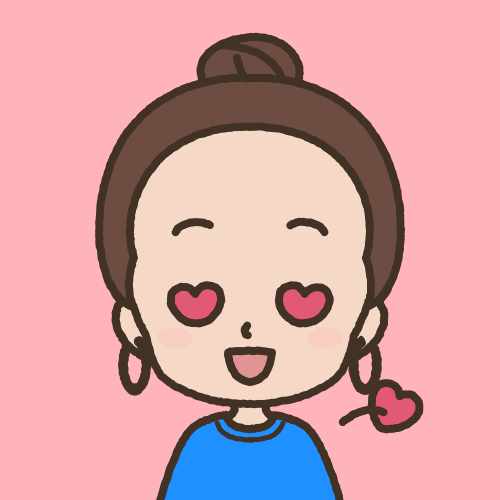
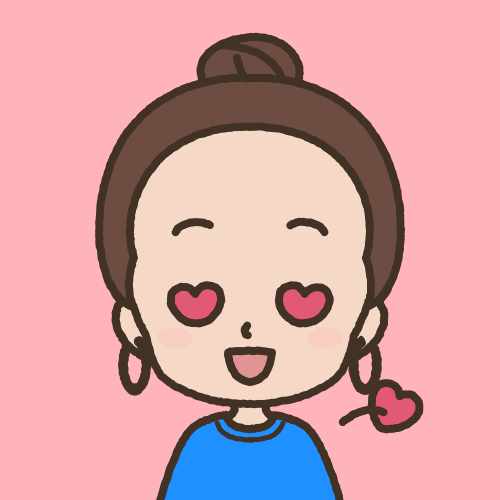
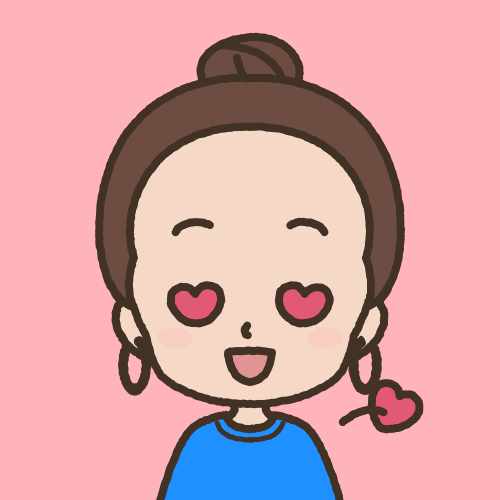
「部活・塾・スマホ代…お金がかかる時期だから、周りの平均も気になる!」
高校生になると交友関係や行動範囲がぐっと広がって、お小遣いの使い道も小・中学生の頃とは大きく変わりますよね。
保護者としては「周りと比べて多い?少ない?」と気になるところ。
この記事では、最新データをもとに**「お小遣い 平均 高校生」のリアルな相場や金額設定のポイント**をわかりやすく紹介します。
また、実際の家庭の体験談も交えながら、無理なく続けられるお小遣いの渡し方も解説します✨
結論
高校生のお小遣いの平均は、全国的に月額5,000〜7,000円程度が主流です。
スマホ代や通学費などを含めるかによって金額は変わりますが、家庭ごとのルールを明確にしておくことが大切です。


お小遣い 平均 高校生の最新データと相場をチェックしよう
高校生になると、行動範囲が広がり、使い道も多様になります。
だからこそ「みんな、いくらもらってるの?」という疑問は、多くの家庭で共通の悩みです。
ここでは、2025年最新版の調査データをもとに、高校生のお小遣い平均額をわかりやすく紹介します。
都市部・地方での違いや、学年別の差もチェックして、家庭での金額設定の参考にしましょう。
高校生のお小遣い 平均金額は月5,000〜7,000円が主流
全国調査によると、高校生のお小遣い平均は月5,000〜7,000円。
1年生は5,000円台、3年生になるとアルバイトを始める生徒も増え、やや高めになる傾向があります。
塾やスマホ代を含めて「まとめて支給」する家庭も多く、単純な比較が難しい面もありますが、平均値を知ることで基準を持ちやすくなります。


都市部と地方で差がある?地域別のお小遣い平均
都市部では交通費や交際費がかかるため、平均が高めになる傾向があります。
例えば東京都内の高校生は7,000〜10,000円という家庭も珍しくありません。
一方で地方は徒歩や自転車通学が多く、支出も少なめ。
そのため平均は5,000円前後になることが多いです。地域の生活スタイルを踏まえると、金額の違いにも納得できますよね。
男子・女子でも差がある?意外な傾向
男子高校生は「趣味・ゲーム」にお金を使う割合が高く、女子高校生は「ファッション・コスメ」への出費が目立ちます。
平均額自体に大きな差はないものの、使い道の違いが金額感に影響しているケースも。
たとえば女子は定期的なコスメ購入や友人とのカフェ代などが重なるため、やや多めに設定する家庭もあります。
お小遣い 平均 高校生を参考に「わが家ルール」を決めよう
平均額を把握したら、次は「わが家のお小遣いルール」を決める段階です。
家庭によって経済状況や教育方針はさまざまなので、平均だけを鵜呑みにするのはNG。
金額だけでなく「どんな使い方をしてほしいか」「何を含めるか」まで考えて、明確なルールを作ることが大切です。
ここでは、お小遣いルールを決めるときの具体的なポイントと実例を紹介します✨


使い道と支給内容を明確にする
まずは、お小遣いに含める範囲をはっきりさせましょう。
例えば「お菓子・遊び代だけ」なのか、「スマホ代・通学費込み」なのかで金額は大きく変わります。
月5,000円を自由費として渡し、スマホ代は別途家計で負担しています。
一方で、月10,000円を一括支給し「その中でやりくり」を経験させる家庭も。
明確な区分があると、親子間のトラブルも減らせます💡
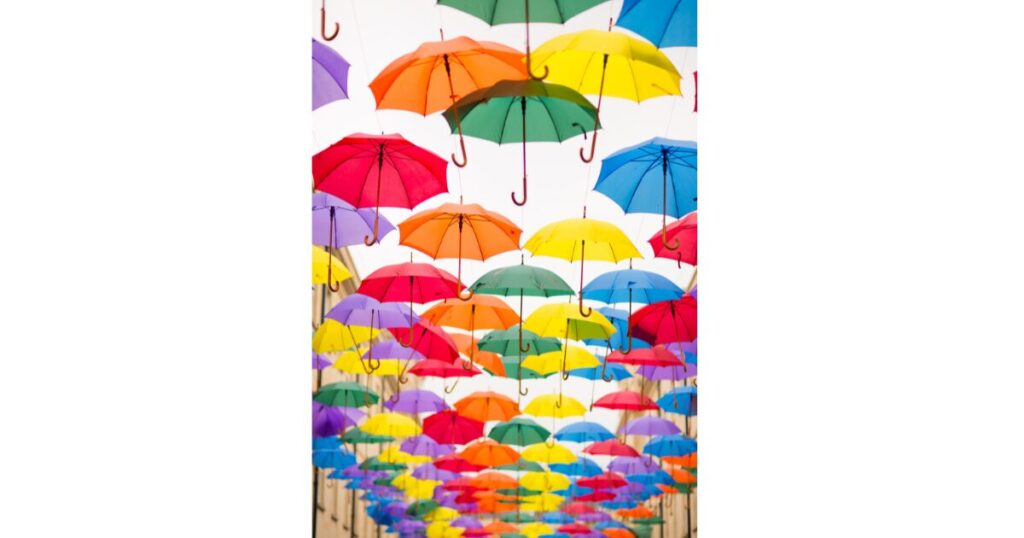
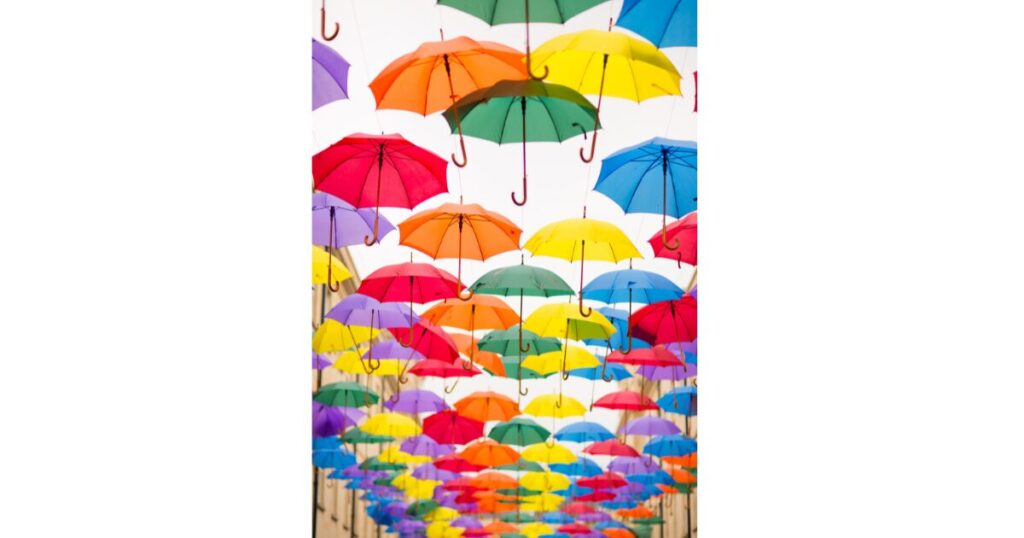
支給日と支給方法を統一する
「いつ・どうやって渡すか」も重要なルールです。毎月1日に手渡し、またはキャッシュレス決済にチャージするなど、家庭に合った方法を選びましょう。
支給日を固定すると、子どもも計画的に使いやすくなります。
実際、毎月まとめて渡す家庭では「使い切りが早くなってしまう」という声もあるため、半月ごとなど細かく分ける工夫も有効です😉
臨時支出の扱いを決めておく
修学旅行や部活の遠征など、臨時でお金が必要になる場面も多い高校生活。
こうした特別な支出を「お小遣いに含めるのか」「別枠でサポートするのか」をあらかじめ話し合っておくと安心です。
ある家庭では「月のお小遣いとは別に、必要経費は申請制」にすることで、無駄遣いを防ぎつつサポートもできています✨
お小遣い 平均 高校生を踏まえた上手な使い方と管理術
お小遣いは「ただ渡すだけ」ではもったいない!使い方を工夫することで、お金の大切さや管理力を自然と身につけられるチャンスになります。
高校生は自由に行動できる分、使い道も幅広く、気づけばあっという間に使い切ってしまうことも…。
ここでは、平均金額を踏まえて、上手にやりくりしながら成長につなげる管理術を紹介します💰✨
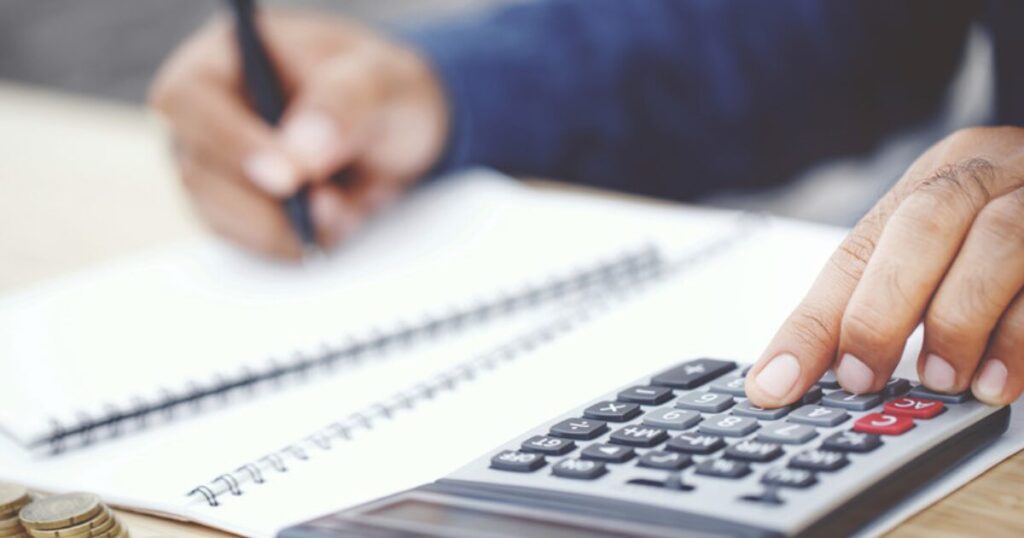
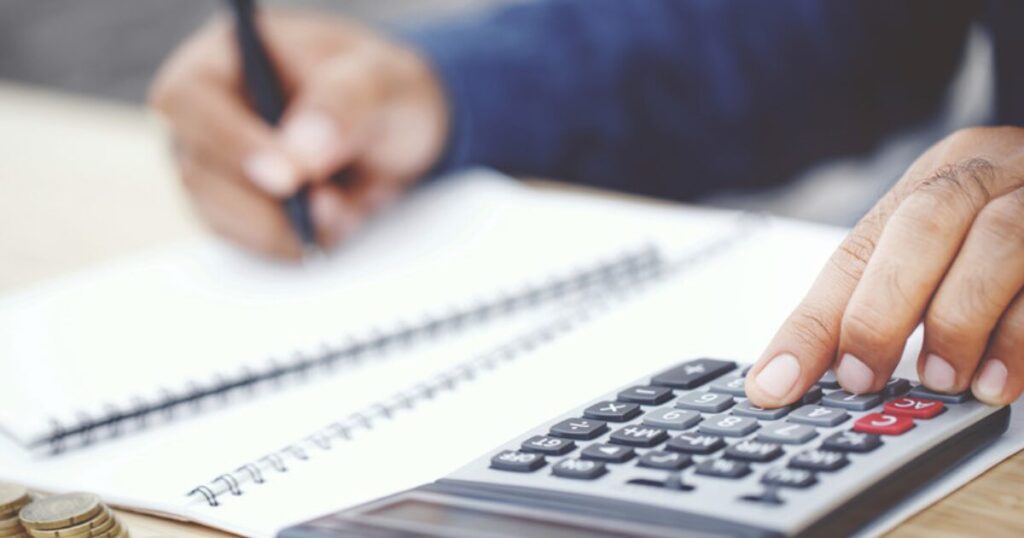
予算を立てて「目的別」に分ける
毎月のお小遣いをもらったら、まず「何に使うか」をざっくりと分ける習慣をつけると◎
たとえば「交際費・趣味・貯金」の3つに分けて管理するだけでも、使いすぎを防げます。
ある女子高生は、月7,000円のうち2,000円をカフェ代、2,000円をコスメ、1,000円を趣味、2,000円を貯金という内訳で使っています。
「何となく使う」を防ぐことで、自分でお金をコントロールする力が身につきます✨
スマホの家計簿アプリを活用する
手軽にできる管理方法として人気なのが、スマホの家計簿アプリ。
高校生でも使いやすい無料アプリが多く、レシートを撮るだけで入力できるものもあります。
実際、家計簿アプリを使っている高校生からは「自分のお金の流れが見えるようになった」「貯金が増えた」という声も。
毎月の振り返りを習慣にすれば、自然と金銭感覚が鍛えられます📱✨
貯金習慣を取り入れる
少額でもコツコツ貯める習慣は、高校生のうちから身につけておきたいポイントです。
たとえば「毎月1,000円だけ貯金」でも、1年で12,000円。
お年玉や臨時収入も合わせれば、ちょっとしたご褒美や将来の資金にできます。
ある男子高校生は、部活を引退した後の旅行資金をお小遣いの貯金でまかないました。
「自分で貯めたお金で行けたのがうれしかった」と話しています😊
お小遣い 平均 高校生とアルバイトの関係を上手に考えよう
高校生になると、アルバイトを始める子も増えてきますよね。
「バイトをしてるならお小遣いはいらない?」という疑問や、「バイトとお小遣いのバランスをどう取る?」と悩む家庭も多いです。
ここでは、平均額を踏まえながら、アルバイトとお小遣いをどう両立させるか、実例も交えて紹介します。
家庭の方針によって考え方はさまざまなので、それぞれのメリット・デメリットを整理しておきましょう☕️✨


アルバイトを始めたら「お小遣いを減らす」?家庭ごとの判断がカギ
アルバイト収入があると、「じゃあお小遣いはゼロでいいかな?」と考える家庭もありますが、一律に減らすとモチベーションが下がることも。
ある家庭では「お小遣いは基本5,000円のまま+アルバイト分は自由に管理」としています。
別の家庭では「バイトを始めたらお小遣いは3,000円に減額」と段階的に調整していました。
子どもの性格や働く目的によって柔軟に対応するのがベストです😉
アルバイト収入とお小遣いの使い分けを明確に
アルバイトで得た収入は、自由に使える分、つい浪費してしまうリスクもあります。
バイト代を趣味や交際費に、お小遣いを貯金に充てるというルールを自分で決め、1年間で3万円以上貯金できたそうです。
親が一方的に決めるより、子どもと一緒に「収入の使い分けルール」を話し合うことで、自立心と金銭感覚の両方が育ちます✨
学業との両立にも注意しよう
アルバイトをすることで得られる経験や収入は大きな魅力ですが、学業への影響には注意が必要です。
実際、「バイトが忙しくて成績が下がった」「部活と両立できなかった」という声もあります。
お小遣いの金額設定と同じくらい、バイト時間や優先順位の話し合いも大切です。
家庭で「テスト期間中はシフトを減らす」など、ルールを設けると安心です📚✨
お小遣い 平均 高校生を学年・男女・地域で比較!リアルな差をチェック
「高校生のお小遣い平均」といっても、全員が同じ金額をもらっているわけではありません。
学年が上がるにつれて交際範囲や支出内容も変わり、男女や地域によっても金額に差があります。
ここでは、最新データをもとに、学年別・男女別・地域別のリアルな傾向をわかりやすく紹介します💡
家庭の方針を考えるうえで、こうした比較はとても参考になりますよ✨
学年別に見るお小遣い 平均 高校生の違い
1年生はまだ交際費や外出が少なく、平均は5,000円前後が中心です。
2年生になると、部活や放課後の活動が増え、6,000〜7,000円になる傾向が。
3年生はアルバイトを始める子も多く、一気に1万円を超えるケースも見られます。
例えば、男子3年生で週2回のバイトをしている場合、お小遣い5,000円+バイト代で月15,000円以上になるケースも珍しくありません👛✨
男女別の平均と使い道の違い
男女で平均額に大きな差はありませんが、使い道にははっきりした傾向が見られます。
男子はゲームや趣味への出費が多く、女子はファッションやコスメ代が目立ちます。
ある女子高生は、毎月のカフェ代とコスメ代で7,000円を使い切ってしまう一方、男子高生は月5,000円をすべてスマホゲームの課金に使っているケースも👦👧✨
使い方の違いが金額感にも影響しているんですね。


地域別の差は意外と大きい!都市部と地方の比較
都市部では交通費や外食費がかさむため、平均金額が高めになる傾向があります。
東京都内では7,000〜10,000円が主流で、塾やスマホ代を含めるとそれ以上になることも。
一方、地方は徒歩・自転車通学が多く、5,000円前後が主流です。
北海道の高校生は「放課後はみんな自転車で遊びに行くから、交通費はゼロ。お菓子代くらい」と話していました🚲✨
お小遣い 平均 高校生を踏まえた保護者の考え方と教育方針
お小遣いは「ただの金額設定」ではなく、家庭の教育方針や価値観が色濃く反映される部分です。
「たくさんあげた方がいいのか」「厳しく制限した方がいいのか」正解は一つではありません。
ここでは、保護者が実際にどのような考え方でお小遣いを決めているのか、教育方針との関係や工夫例を紹介します👪✨
家庭ごとの方針をしっかり持つことで、子どもの金銭感覚を健全に育むことができます。
お小遣いは「金銭教育」の第一歩と考える
多くの保護者が、お小遣いを「お金の使い方を学ぶ機会」として位置づけています。
ある家庭では「月5,000円の中で計画的に使う」経験を通して、子どもが自然と予算管理を覚えるようになりました。
高校生のうちから「使う・貯める・計画する」を意識させることで、将来の金銭感覚に大きな差が出ます✨


金額よりも「渡し方・話し合い方」が重要
保護者の中には「金額は少なめでも、毎月一緒に振り返る時間を大切にしている」という家庭もあります。
例えば、月末に「今月どうだった?」と話す習慣を持つだけで、親子のコミュニケーションが深まり、無駄遣いも減る傾向にあります。
「渡す→終わり」ではなく、話し合いを通して考える時間を持つことが教育的効果を高めます💬✨
家庭の価値観をしっかり共有する
「お金は湯水のように使うものではない」「計画的に使うことを大切にしてほしい」など、家庭の価値観を明確にしておくと、子どもも納得しやすくなります。
両親が自分たちの高校時代の経験を話しながら、なぜ今の金額設定なのかを伝えていました。
背景を共有することで、押しつけにならず理解が深まります😊
お小遣い 平均 高校生を参考に「渡し方・頻度・形式」を工夫しよう
お小遣いは金額だけじゃなく、**「どう渡すか」や「どんな頻度で支給するか」**によっても子どもの使い方や意識が大きく変わります。
高校生になると自分で管理できる範囲が広がるので、家庭ごとに合った渡し方を工夫するのがポイントです。
ここでは、現金・キャッシュレス・定期支給など、具体的なスタイルとそのメリット・デメリットを紹介します💰✨
現金派のメリットと注意点
昔ながらの現金支給は、手に取って金額を実感しやすく、金銭感覚を身につけやすいというメリットがあります。
ただし「財布の中にある分、全部使ってしまう」という高校生も多く、計画性を育てるためには一緒に予算の組み方を話すことが大切です。
封筒を3つに分けて「交際費・趣味・貯金」と分けて渡すことで自然と管理力が身についたそうです📌✨
キャッシュレス派は時代に合った管理方法
最近ではキャッシュレス派も増加中。交通系ICカードやスマホ決済にチャージして渡す方法は、通学や買い物に便利です。
「履歴が残るので、どこで使ったか把握しやすい」「無駄遣いが減った」という声もあります。
一方で、残高が見えにくく、使いすぎてしまうケースもあるため、アプリなどで管理方法を教えると安心です📱✨


頻度を調整して計画力を育てる
毎月まとめて渡すと計画力が必要になりますが、使い切ってしまう子には半月ごと・週ごとなど頻度を細かく設定する方法もおすすめです。
月1回支給だとすぐに使い切ってしまっていたのを、週1回にしたことで浪費が減り、貯金までできるようになりました。
子どもの性格や行動パターンに合わせて柔軟に対応するのがコツです😉✨
お小遣い 平均 高校生を踏まえてトラブルを防ぐコツを知ろう
お小遣いは、親子のコミュニケーションや信頼関係にも大きく関わります。
金額が適切でも、ルールや話し合いが不十分だと「使いすぎた」「もらいすぎ」「足りない」など、トラブルにつながることも…。
ここでは、高校生のお小遣いでよくあるトラブルと、その防ぎ方を具体例とともに紹介します💡
ちょっとした工夫で、親子どちらも気持ちよく続けられる環境が整います✨
「使いすぎ」を防ぐための声かけと習慣づくり
「もらった分、全部使ってしまう…」という高校生は少なくありません。
対策として効果的なのが、使い道の見える化と定期的な話し合いです。
ある家庭では、月1回の振り返りタイムを設定し、レシートやアプリを一緒にチェックすることで「今月はここが無駄だったね」と話し合えるようになりました。
怒るのではなく、一緒に考える姿勢がポイントです😊✨
「もらいすぎ・足りない」問題は家庭の価値観を共有
友達と比べて「うちは少ない」と感じる高校生もいれば、「多すぎて使い方が雑になる」ケースもあります。
家庭ごとの方針をしっかり話しておくと、こうした不満や甘えを防ぎやすくなります。
実際、「なぜこの金額なのか」を伝えるだけで、子どもの納得度がぐっと上がったという保護者の声もありました👪✨
トラブルが起きたときは「一緒に見直す」スタンスで
トラブルが起きたときに感情的に叱るだけでは、根本的な解決にはなりません。
「どうしてそうなったか」「次はどうするか」を一緒に考えることで、金銭感覚も親子の信頼も育ちます。
つい衝動買いをしてしまった経験をきっかけに、予算管理アプリを使い始め、今では自分で計画を立てられるようになりました📈✨
お小遣い 平均 高校生を通して身につけられる力とは?
お小遣いは、単なる「お金のやり取り」ではなく、将来に役立つ力を育むチャンスです💡
計画的な使い方や、自分で管理する経験を積むことで、社会に出たときに必要な金銭感覚や責任感が自然と身につきます。
ここでは、高校生がお小遣いを通して得られる力を具体的に紹介します✨
家庭で意識してサポートすることで、子どもの成長がグッと広がります!
計画力と判断力が身につく
限られたお小遣いをどう使うかを考える過程で、計画性と判断力が磨かれます。
たとえば「今すぐ欲しいけど我慢して貯める」経験を通して、優先順位を考える力が育ちます。
毎月の小遣いから少しずつ貯めて自転車を購入、と「自分で決めて貯めた達成感がうれしかった!」と話していました😊✨
金銭管理力と自己コントロール力が育つ
家計簿アプリや封筒分けなどの管理方法を実践することで、お金の流れを把握し、自己管理の力が育ちます。
「もらった分を全部使う」から「どう使うかを考える」姿勢に変わるのは大きな一歩。
高校生のうちからこの感覚を身につけておくと、社会人になってからの家計管理にも大きな差がつきます💪✨
親子でお金について話すきっかけになる
お小遣いを通して「お金の話」を自然にできる環境が生まれます。
「今月どうだった?」「何に使ったの?」といった会話を積み重ねることで、信頼関係が深まり、価値観の共有にもつながります。
毎月の振り返りタイムがきっかけで、子どもが将来の夢や進路について話すようになったそうです🌱✨


お小遣い 平均 高校生を踏まえて、家庭に合ったルールを見つけよう
ここまで、高校生のお小遣いの平均額やルールの決め方、管理のコツなどを紹介してきましたが、最も大切なのは「家庭に合った形を見つけること」です✨
平均額はあくまで目安であり、金額よりも家庭の方針・話し合い・信頼関係が重要です。
お小遣いは、子どもの金銭感覚を育て、親子のコミュニケーションを深める大切なツール。
無理のない仕組みを作って、長く続けられる形にしていきましょう😊
まとめ
高校生のお小遣いの平均は、全国的に月5,000〜7,000円が主流です。
ただし、学年・地域・男女・家庭方針によって金額や渡し方はさまざま。
大切なのは、平均を参考にしながら、わが家らしいルールと使い方をしっかり話し合って決めることです。
アルバイトやキャッシュレスの活用、定期的な振り返りを組み合わせることで、トラブルを防ぎつつ、子どもの成長にもつながります🌱✨
📌 安定した未来のため資産形成やライフリスクは【ファイナンシャルプランナーに相談】
高校生のお小遣い管理は、実は「家庭のお金の話」を始める良いきっかけでもあります。
家計の見直しや将来の資産形成も、専門家に相談することで安心して進められます。
プロのFPに相談して、家族の未来を一緒に考えてみましょう💪✨
よくある質問(FAQ)
- 1. 高校生のお小遣いはいつから渡すのがいい?
-
高校入学時にスタートする家庭が多いです。生活範囲が広がるタイミングでルールを明確にするとスムーズです。
- 2. アルバイトを始めたらお小遣いはゼロにすべき?
-
一律にゼロにするのではなく、性格や目的に合わせて調整するのがおすすめです。
- 3. 現金とキャッシュレス、どっちがいい?
-
それぞれメリットがあるため、家庭や子どもの性格に合わせて選びましょう。併用する家庭も増えています。
- 4. 使いすぎが気になるときは?
-
責めるより一緒に振り返る時間をつくると、改善しやすくなります。家計簿アプリの活用も効果的です。
- 5. 平均より少ないと子どもが不満を持ちそうで不安…
-
金額の理由や家庭の方針をしっかり伝えることで、納得感が生まれやすくなります。「なぜこの金額なのか」を話すことがポイントです。