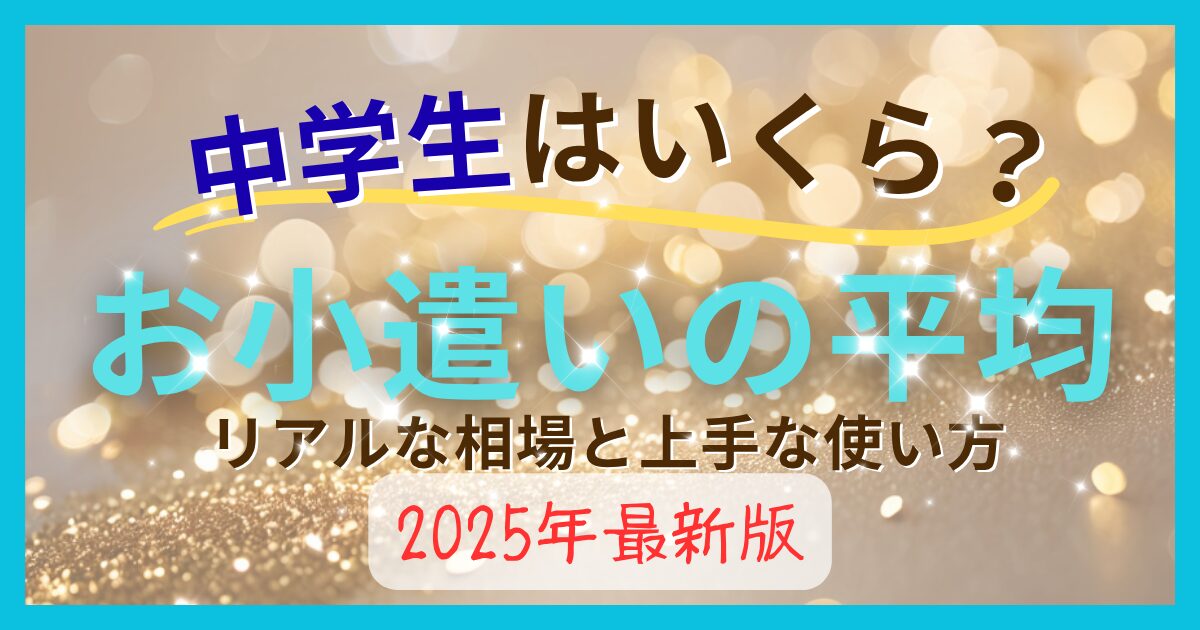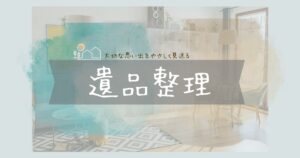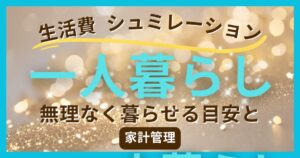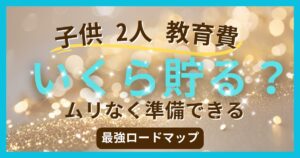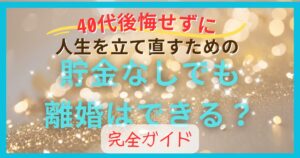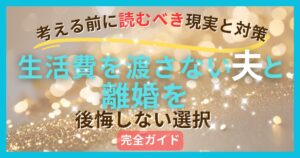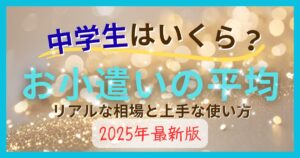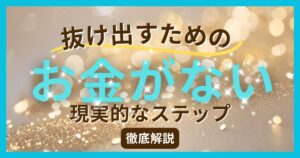ラザ
ラザ「うちの子のお小遣い、みんなと比べて多い?少ない?」



「金額だけじゃなく、渡し方も気になる…」



「将来の金銭感覚、今から育てたい!」
中学生を持つママとして「うちの子のお小遣いって他の家庭と比べてどうなんだろう?」と感じたこと、ありますよね。お金の与え方ひとつで子どもの金銭感覚が育つから慎重になるもの。この記事では「お小遣い中学生平均遣い」をキーワードに、相場、使い道、ルール作りのコツまで、役立つ情報をまとめてみました。
最新調査で見る全国平均と地域差
都市部と地方でこんなに違う中学生のお小遣い
最新の家計調査によると、中学生のお小遣いは全国平均で月1,500円〜3,000円ほどやけど、実は地域差がはっきりしてる。例えば首都圏では交通費や外食の機会が多い影響で、月3,000円以上もらっている子が約4割を占めるという結果も出てる。一方、地方では自転車通学や家の近所で遊ぶ子が多く、月1,500円程度が主流という声も多い。住んでる地域の生活スタイルで必要なお金が変わるのを実感。まずは平均額だけやなく、地域ごとの暮らしを基準に考えるのが大事。


学年ごとの違いと成長による必要経費
学年が上がるにつれて、お小遣いが自然に増える家庭も多い。1年生ではまだ部活の費用や友達との外出も少なく、月1,500円程度で十分という声が目立つ。けど2年生になると部活の試合や塾の自習で帰りが遅くなり、帰り道に軽食を買う機会も増えるから2,000円〜2,500円が相場に。3年生は受験勉強の合間にカフェで友達と勉強するなど外で使う場面が増えて、3,000円以上に上げたという家庭もある。わたしの子供の場合には1年生から3,000円を足して、使わない時には貯金へ。「3年生は受験だったから、1、2年生の時の方が使ったなー。」と言っていました。部活帰りに友達と寄り道する楽しみが増えて「お金のやりくりを考えるようになった」と言ってて、成長を感じた瞬間も。
定額制と必要時支給制で違う金銭感覚
お小遣いの渡し方にも家庭差があって、月初にまとめて渡す定額制と、必要な時に都度渡すスタイルに分かれるんや。定額制は計画的に使う力がつきやすい反面、初めの数日で使い切ってしまった時にどう過ごすかが学びどころ。必要時支給制は無駄遣いは減るけど、子どもが自分で予算を立てる機会は少なくなる。どちらの方法にもメリットがあるから、家庭の教育方針に合わせて選ぶのがポイント。


金額を決める前に考える3つの視点
1.家計の余裕度と家庭の優先順位を整理する
お小遣いの金額を決める時、一番に考えたいのが家計全体のバランスや。毎月の生活費や貯金計画を踏まえたうえで、「教育費を優先する」「旅行費を積み立てたい」など家庭の優先順位を整理してから金額を決めると安心。例えば我が家では住宅ローンの繰上げ返済を進めている時期は、お小遣いは少し抑えめにして、外食回数を増やしてあげるなど別の形で子どもへの還元を意識。お小遣い額だけを見ず、家族の将来プランと合わせて話し合うと、子どもも「家のお金には限りがある」と自然に学べる。
2.子どものお金に対する理解度を見極める
同じ中学生でもお金の扱い方は人それぞれだから、理解度を見極めて金額を調整するのも大切。例えば上の子はは小学生時代からお小遣い帳を自分でつけて計画的に使うタイプ。中学に入っても月2,000円をきちんと管理できていたから、親も安心してそのままの金額を続けられた。一方、下の子は最初にまとめて使ってしまうクセがあり、月1,500円からスタートして「半分は貯金」と約束を作ったとか。子どもの理解度に合わせたステップアップが、金銭感覚を育てる近道に。
3.お小遣いの目的を親子で共有する
最後に大切なのは、お小遣いの目的を親子でしっかり共有すること。「友だちとのお付き合いのため」「自分の欲しい物を買うため」など、何に使うかを一緒に話し合うと、金額をどう設定するかも決めやすくなる。上の子は「毎月の中から2割は貯金に回す」という目標を一緒に決めた。最初は不満そうやったけど、半年後には貯金がちょっとずつ増えていくのを喜び、自分で計画を立て始めた。目的を共有すれば、お小遣いは単なるお金以上の学びに。
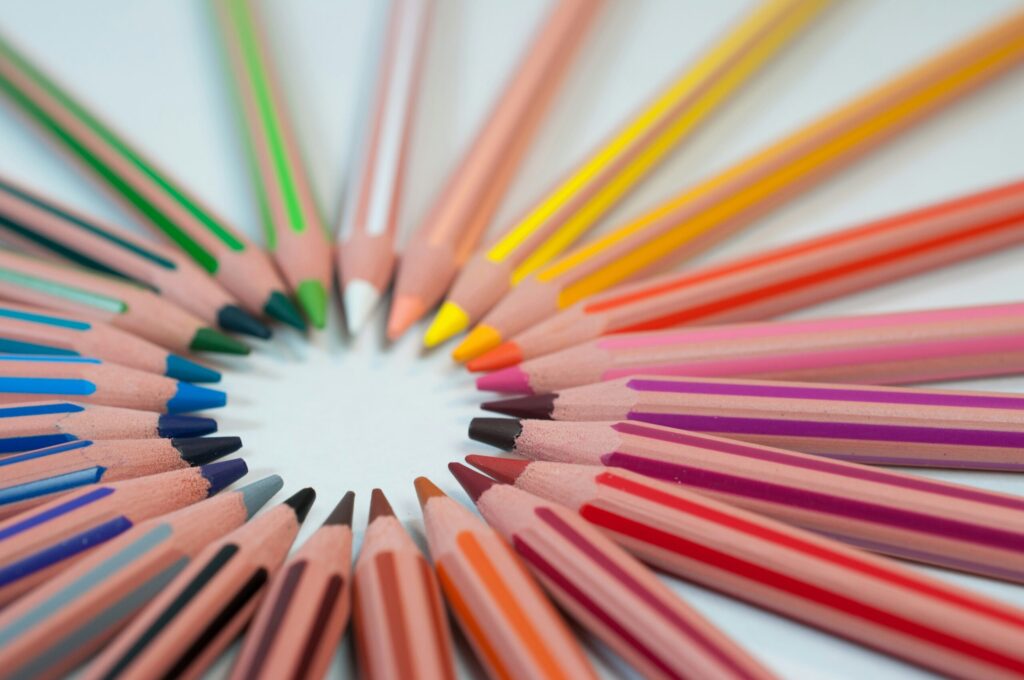
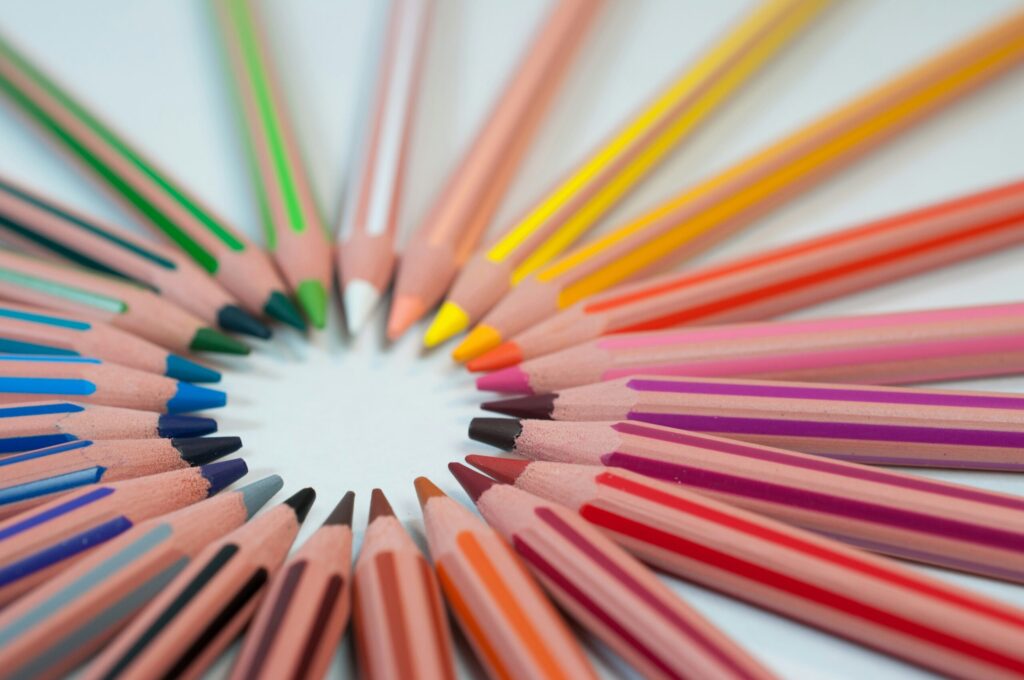
学年別に見る金額の変化と理由
1年生はまだ少額でも十分や
中学1年生はまだ小学生の延長みたいな生活スタイルで、放課後も友だちの家で遊ぶことが多いから、お小遣いは月1,500円前後でも十分という家庭が多い。上の子も1年生の頃は友だちと公園に遊びに行くくらいで、週に数百円あれば楽しめてた。最初は「少ないかな」と思ったけど、自分で計画的に買う練習ができたし、「次は何を買うか」を考える習慣が自然に身についた。少額でも子どもが満足できる使い道を一緒に見つけてあげることが大事。
2年生は交友関係が広がり出費が増える
2年生になると部活や友だちとの付き合いが活発になって、遊び帰りにコンビニでお菓子を買ったり、休日に映画を見に行ったりとお金を使う機会が一気に増える。「次の週のために少し残そう」と計画的に使い始めた。交友関係が広がる時期こそ、お金の使い方を学ぶチャンス。


3年生は受験期に合わせた臨時対応も必要
3年生になると受験勉強が本格化して、友だちと図書館や塾で勉強する機会も増える。この時期はほとんどお金を使わずに過ごすことが多かったので、「お金が貯まるー!」と喜んでました。
渡し方のスタイルで金銭感覚が変わる
月初にまとめて渡す定額制で計画性を育てる
月初にまとめてお小遣いを渡す定額制は、子どもが自分で計画を立ててお金を管理する力を養いやすい。我が子も1年生の頃から月3,000円を月初にまとめて渡してたけど、最初は数日で使い切ってしまって「あと20日どうしよう」と頭を抱えていることも。そこで「1週間ごとに使える金額をメモしてみたら?」と声をかけたら、翌月からは無駄遣いが減って、欲しい本も自分で買えるようになったり。定額制は計画性と自己管理を学ばせる良いきっかけになる。
必要な時に渡すその都度制で無駄を抑える
一方、必要な時に必要な分だけ渡すその都度制は、親がコントロールしやすく無駄遣いを防ぎやすい。我が家では子供が小学生の頃、週末に必要な分だけ渡すスタイルを採用。例えば「友だちと映画に行くから1,000円欲しい」と相談してきた時に渡す形。この方法は急な出費に柔軟に対応できるけど、息子自身は予算を立てる経験が少なかったせいか、中学に入って定額制に切り替えた時に最初は戸惑ってた。無駄は減るけど、計画性を身につけるには工夫が必要。


ハイブリッド型で家庭に合ったバランスを
最近は定額制とその都度制を組み合わせたハイブリッド型を選ぶ家庭も増えてる。例えば月2,000円は毎月決まって渡し、部活の遠征や友だちの誕生日プレゼントなど特別な時は追加で渡す方法や。我が家でも娘が2年生になった頃からこのスタイルに変更。通常は月2,000円でやりくりさせつつ、部活の大会で遠征する時だけ1,000円追加。子どもは「これで普段のやりくりも頑張れるし、特別な時は気持ちに余裕ができる」と喜んでた。柔軟に対応できるハイブリッド型は、家庭のライフスタイルに合わせやすい。
使い道から学ぶ金銭感覚の育て方
友だちとの外出で学ぶ計画性
中学生になると友だちと外食や買い物に行く機会が増える。わたしの子ども2年生の頃から放課後にファストフード店でおしゃべりすることが多くなり、1回500円前後の出費が増えた。最初は月2,000円のお小遣いをすぐに使い切ってしまったけど、「週に何回まで外食できるか」を一緒に計算したことで、1回の出費を抑える工夫を自分で考えるようになった。例えばドリンクだけ頼んで長くおしゃべりするなど、クーポンを使ってみたり、自分なりに調整して楽しんでた。友だちとの外出は、ただの遊びやなく計画的にお金を使う練習の場にもなる。
趣味や推し活で芽生える自己投資の意識
最近の中学生は推し活や趣味にお金を使うケースも増えてる。我が家の息子も好きなラップグループのCDやライブ配信チケットにお小遣いをコツコツ貯めて使ってた。初めは衝動買いが多かったけど、「このCDを買うにはあと2ヶ月我慢しよう」と自分で計画を立てるように変わっていったり。好きなことにお金を使う体験は、自己投資の大切さや目標に向けて貯める習慣を自然と学べる。趣味を通してお金の価値を知ることは、将来の資産形成にもつながる大きな一歩に。


親子でルールを決めるメリット
ルールを一緒に作ることで責任感が育つ
お小遣いをただ渡すだけやと、子どもは「使って終わり」になりやすい。わたしは子どもの性格に合わせて一緒に「毎月の8割は自由に使い、2割は貯金する」というルールを作ったん子も。最初は「貯金か〜」と言っていたけど、自分でルール決めに参加したことで「守らなきゃ」という責任感が芽生えた様子。ある月は欲しい漫画を我慢して貯金を優先したり、自分なりに工夫してた。ルール作りを親子で共有すると、子どもはお金を使うだけでなく計画を立てる責任を学べる。
家庭ごとの価値観を話し合うきっかけになる
ルールを決める過程は、家庭の価値観を伝える絶好のチャンス。我が家では中学生からは「誕生日やお正月に臨時で渡すお年玉は本人任せ」と話し合った。親の価値観を押し付けるのではなく、子どもに理由を説明して一緒に考える時間が、家族の絆を深めてくれる。
トラブル防止と親子の信頼関係アップ
親子でルールを決めておくと「もっとちょうだい」「足りない」といったトラブルを防ぎやすい。足りないと重時には事前に相談して欲しいことを伝え、自分で計画を立てるようになり、「次はこれに使いたい」と事前に相談してくるようになった。親子間の信頼関係が深まり、お金のやり取りもストレスが減った。


失敗から学ぶお金のレッスン
最初の月に使い切った体験から学ぶ
わたしの子どもが中学に入って初めて月3,000円を渡された時、数日でお菓子やカードゲームに全部使い切ってしまったんや。月末に友だちと出かける約束をしていたのにお金がなく、「次は計画的に使わなきゃ」と自分から反省してた。そこで一緒に「1週間に使える上限を決めよう」と相談し、翌月からは自分で考えてペース配分できるようになり、お金の計画性が一気に育った。
友だち付き合いで見栄を張った失敗
友だちに合わせて毎週カフェでスイーツを頼み続けた結果、月半ばでお小遣いが尽きてしまったんや。「みんなが頼んでるから」と言ってたけど、後から「無理して合わせても楽しくなかった」と反省。次の月からはドリンクだけにして、残りは自分の好きな本に回すようになった。見栄を張った失敗を通じて、本当に大切にしたいものを見極める力を身につけた娘の成長を感じた。
親のフォローが次への学びを深める
失敗をただ叱るだけやと子どもは萎縮してしまう。お金を使い切った時に「次はどうしたい?」と聞くだけにとどめた。「週ごとの上限を決めたい」と提案してきて、その後は自分から管理方法を工夫するようになった。親がフォローして次へのステップを一緒に考えることで、子どもは失敗を恐れず挑戦し続けられる。失敗を学びに変える姿勢は、将来の資産形成にも必ず役立つことを実感。


将来の資産形成につながる教え方
毎月の貯金習慣で将来の計画性を育てる
中学生のうちから毎月少しずつ貯金する習慣を身につけると、将来の資産形成に大きな差が出る。「毎月のお小遣いの2割は貯金」というルールを作った。最初は「2割くらいならいいか」と気軽に始めた娘やけど、半年後に貯金が3,000円を超えた時に「これで好きな本を一気に買える!」と嬉しそうにしてた。その後も自分から「次は5,000円貯める」と目標を立てて継続。小さな習慣が大きな自信になり、計画的にお金を増やす感覚を育てられた。
投資や経済ニュースに興味を持たせる
お小遣いをきっかけに投資や経済に関心を持たせるのも大切や。学校の授業で株式投資のシミュレーションを体験。その後「実際の株価ってどう動くの?」とニュースを自分からチェックするようになった。わたしも一緒にネット証券のサイトを見ながら「この会社はどう成長するかな」と話し合ったわ。実際に投資を始めなくても、経済の仕組みに興味を持つだけで将来の資産形成への理解が深まる。
家族でライフプランを共有して未来を描く
将来の資産形成を考えるには、家族全体でライフプランを話し合うことも大切。我が家では「高校卒業後に大学進学したらどのくらいお金がかかるか」を子どもと一緒に調べた。「大学ってこんなに学費が必要なんだ」と驚いて、自分の貯金を「将来の学費に使いたい」と言ってた。家族で未来のビジョンを共有すると、子どもも自分の役割を実感して、お金を長期的に考える力が自然と身につく。
家族みんなでお金の話を続ける大切さ
毎月の振り返りで学びを積み重ねる
お小遣いを渡して終わりやなく、毎月の使い道を親子で一緒に振り返る習慣が大切や。わたしは月末に「今月はどんな使い方をした?」と一緒にアプリを見ながら話す時間を作ったん。最初は「特に何も考えてない」と言っていた子も、次第に「来月は本を買うために1,000円残す」と自分から目標を語るようになった。小さな振り返りを続けることで、子どもは計画性と反省する力を自然に身につけていく。


家族全体のライフプランを共有する
お小遣いの話をきっかけに、家族全体の将来計画を共有するとお金への理解がぐっと深まる。我が家では「高校卒業後に必要な学費」や「家族旅行の積立目標」などを子どもたちと一緒に話した。「旅行資金に自分もお小遣いから少し貯金する」と提案してくれて、家族の一員として未来を支える意識が芽生えた。こうした会話を通して、子どもは自分の役割を感じながらお金を長期的に捉えられるようになる。
親の体験談を共有してお金の価値を伝える
親自身の体験談を話すのも、子どもにとって大きな学びになる。わたしは「学生時代にアルバイトで初めて貯めたお金で旅行した話」をよく子どもに聞かせる。「自分も将来は自分のお金で好きなことをしたい」と目を輝かせてた。親が経験を語ることで、お金を得る大変さや使う喜びをリアルに感じさせることができる。単なる数字ではなく、お金に込められたストーリーを共有することが、子どもの金銭感覚を豊かに育てるきっかけに。
将来へつながるお金教育を家庭で続ける方法
親子で目標貯金を設定して長期視点を育てる
子どもが将来大きな夢を持ったときに、自分で計画的にお金を準備できる力を育てたいですよね。「高校生になったら自分のお金でパソコンを買いたい」と言い出したので、毎月のお小遣いから500円を目標貯金として別に貯めるようにした。目標を決めて半年後には貯金額が3,000円を超え、「自分で貯められる!」と自信をつけてた。この習慣が高校入学後のアルバイト代の管理にも生きてる。
家族会議でお金の使い方を共有する習慣
毎月一回でも「家族会議」としてお金の使い方や家計の目標を共有するだけで、子どもはお金を現実的に捉えやすくなる。我が家では「今月の支出と来月の目標」を簡単に話す場を作ってるこうした話し合いが、お小遣いをただの小銭やなく「家族で築く未来の一部」と感じさせてくれる。
金融知識を遊びながら学べる教材を取り入れる
最近は中学生向けにゲーム感覚で金融リテラシーを学べる教材やアプリが増えてる。株式投資のシミュレーションゲームを一緒にやってみたら、「株価ってこう動くんや」と興味を持ってニュースもチェックするようになった。遊びながら学べる環境を取り入れると、お小遣いの使い方だけでなく将来のお金の増やし方にも自然と関心が湧く。
よくある質問(FAQ)
Q1. 中学生のお小遣いの平均額はどれくらい?
A. 最新の全国調査では、月額1,500円〜3,000円がボリュームゾーンや。地域差や学年によって上下するけど、だいたいこの範囲を目安にすると安心。
Q2. お小遣いを渡すタイミングは月初がいい?
A. 月初にまとめて渡す家庭が多いけど、必ずしも固定でなくても大丈夫。週単位で渡して管理を覚えさせるのも良い方法。
Q3. お小遣い帳はつけさせた方がええの?
A. つける習慣はおすすめ。簡単なアプリや手書きノートでもいいから、入出金を記録することで計画性が自然に身につく。
Q4. 部活や塾の出費はお小遣いに含める?
A. 学校生活に必要な費用は基本的に家計から出す家庭が多いで。お小遣いは自分の楽しみやちょっとした買い物に使わせる方が、メリハリがつく。
Q5. 金額を増やして欲しいと言われたらどうする?
A. すぐに増やす前に、今のお小遣いの使い方を一緒に振り返ろう。計画的に使えていたら、学年が上がるタイミングで少しずつアップするなど家庭ごとのルールを決めると良いです。


まとめ
中学生のお小遣いは「ただのお金」やなくて、子どもの金銭感覚や将来の資産形成の第一歩や。家庭の状況に合わせて金額を決め、親子でルールや振り返りを重ねることで、お金に対する考え方はしっかり育っていく。
安定した未来のため資産形成やライフリスクは【ファイナンシャルプランナーに相談】がおすすめ!
→ご相談はこちら